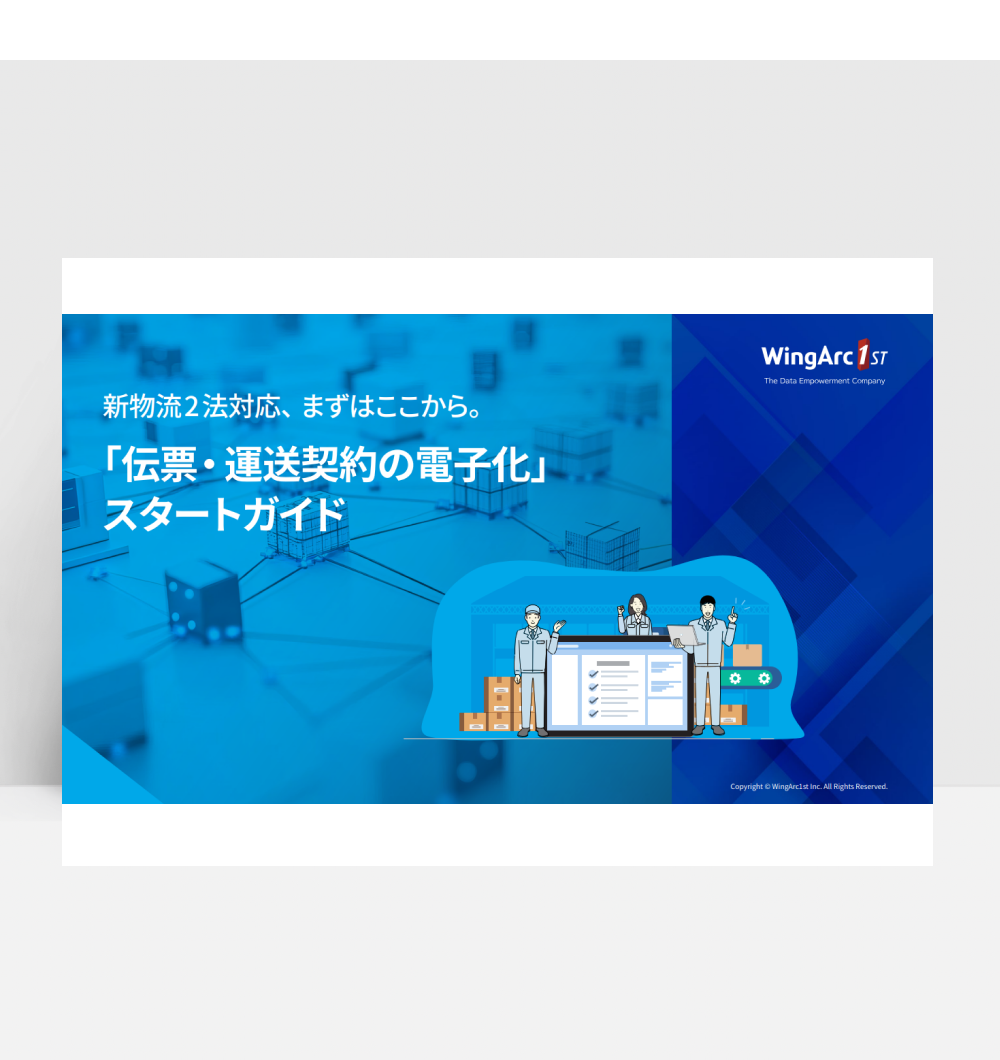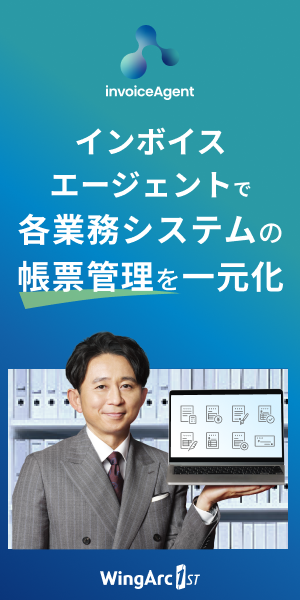運送契約の書面化が求められる背景
はじめに、なぜ書面化の必要性が高まっているのか、その背景と目的を整理するとともに、従来の契約慣習がもたらす具体的なリスクを確認していきましょう。
法改正による背景と目的
2024年4月から施行された「時間外労働上限規制(年960時間)」により、トラックドライバーの労働環境は大きく変わっています。慢性的な人手不足に加え、長時間労働の是正が急務となっている物流業界では、ドライバーの拘束時間が制約される一方で、消費者ニーズはますます多様化しています。
こうした状況を踏まえ、国土交通省は「適正な契約条件の明確化によって、トラブル防止や労働時間短縮につながる」と判断し、運送契約の書面化を義務とする法改正に踏み切りました。実際、口頭やFAXのみで契約を結ぶ商慣習では、運賃や荷役作業、待機時間の扱いが曖昧になりがちです。その結果、過酷な条件での輸送や自主荷役を強いられ、ドライバーの過労やサービス残業的な状態が続いてきたケースも報告されています。
こうした事態を解消し、トラック運賃の適正収受と安全確保を徹底するために、契約書面化の義務化が打ち出されたというわけです。
違反時には行政処分のリスクも
運送契約の書面化は、国土交通省の貨物自動車運送事業法において、2024年の法改正により法的義務として明記されています。単なる推奨やガイドラインではなく、対応しなければ行政処分の対象となる可能性がある点に注意が必要です。
国土交通省の「改正貨物自動車運送事業法Q&A」では、以下のように明示されています。
「罰則はありませんが、貨物自動車運送事業者についてはトラック法第33条に基づく行政処分の対象となる可能性があります。また、荷主についてもトラック・物流Gメンによる是正指導の対象となる可能性があります。」(引用:改正貨物自動車運送事業法Q&A)
この行政処分には、6カ月以内の事業停止命令や、事業許可(第3条許可)の取消しといった重い措置も含まれます。とくに、書面化対応が形式的・不完全なまま放置されていた場合、違反と見なされて事業継続に影響を及ぼす可能性もあります。
“努力義務”ではなく、明確な“義務”として定められた対応である以上、必ず取り組む必要があるという認識が求められます。
従来の口頭契約や慣習がもたらす問題点
多くの企業では、「これまで大きな問題は起きていない」「口頭やメールで十分対応できている」と感じているかもしれません。しかし、実態として以下のようなリスクが潜んでいます。
料金の不明確さ
荷主と運送事業者の間で、荷役作業や付帯業務の有無、荷役作業の対価となる料金の設定などの有無をあやふやにしたまま取引を行うと、後になって請求金額をめぐるトラブルが起こりやすくなります。
不測の事態における責任所在の不透明
事故や貨物の破損が起きた際に、契約範囲や荷役負担が口頭ベースだと、どのように責任を負うのかが曖昧になりやすく、最終的に法的争いに発展する恐れが高まります。
ドライバー負担の増加
曖昧な契約のもとで「急な荷役作業への対応」や「長い待機時間でも運賃据え置き」といった扱いが常態化していました。これは、運送の対価である「運賃」の中に、荷役作業や待機時間といった本来は別途請求されるべき作業の対価がすべて含まれているという習慣が背景にあります。
特に問題となっていたのが、発荷主と元請事業者の間でのみ契約内容が共有され、着荷主には作業内容や運送条件が十分に伝わっていなかったことです。その結果、着荷主はドライバーの業務範囲を正しく把握できず、「指示すれば対応してもらえるもの」として作業を依頼することが慣習化し、本来契約に含まれていない荷役作業を“サービス”として実施させる自主荷役が常態化。ドライバーの過重労働につながっていたのです。
このような状況を改善するため、国土交通省が「運送契約の書面化」を強く要請し、最終的に義務化へと踏み切りました。これは、業界全体の生産性や安全性を高める上で大きな一歩といえます。
運送契約の書面化によるメリット
![unsoukeiyakushomenka_02[1].jpg](../../../img/blog/images/unsoukeiyakushomenka_02%5B1%5D.jpg)
次に、契約を文書化することで具体的に得られるメリットを見ていきましょう。トラブル回避から労働環境の改善まで、多方面にわたる恩恵が期待できます。
トラブル防止とコンプライアンス向上
運送契約をしっかり文書化しておけば、双方が合意した条件が明確に残るため、後になって「言った、言わない」の水掛け論が起きにくくなります。たとえば、運送料金に含まれるサービスの範囲や待機時間、荷役作業の扱い、運賃改定の条件などが契約に盛り込まれている場合、契約外の要求があっても冷静かつ合法的に対応しやすくなります。
さらに、契約内容をあらかじめ明文化しておくことは、社内のリスクマネジメントの向上にも直結します。監査や取引先によるリスク審査で、正式な運送契約書があるかどうかは企業の信頼度を示す基準にもなります。
適正運賃と料金の明確化
運送業で長年課題とされていたのが、「荷役・附帯業務」や「待機時間」の扱いです。荷主都合で長時間の荷待ちが発生しても、従来は運賃に含まれるとみなされ、追加料金の支払いが認められないケースが少なくありませんでした。
しかし、書面化された契約であれば、待機時間料(手待ち料)や荷役作業料、燃料サーチャージなどを事前に明示できるため、運送会社は適正な運賃・料金を収受し、荷主も納得のいく形でコスト管理が可能になります。結果的に両者の信頼関係を損なわず、円滑な取引を継続できるメリットがあります。
業務効率化と労働環境改善への貢献
運送契約の内容を明確に設定することで、配車計画やドライバーのスケジュール管理が精密化できます。積み込み開始から作業完了までの目安や、着荷先での待機時間の見込みなどを事前に共有しておけば、ドライバーの拘束時間を削減し、無用な残業を抑制する効果が高まります。
契約を基盤にして業務内容や賃金が安定すれば、ドライバーにとって働きやすい環境が整い、離職率の低減にもつながります。特に2024年以降、ドライバー不足は一段と深刻化が予想されるため、運送契約の書面化を通して企業の魅力を高めることは重要です。
書面化を推進するうえでの課題と対策
続いて、書面化を導入する際に直面しやすい主な課題と、対処する方法を具体的に見ていきましょう。物流業界ならではの多重下請構造やアナログ慣習などが障壁となることが多いため、それぞれの対応策を整理していきます。
物流業界全体の多重下請構造
物流業界では、元請・一次下請・二次下請といった複数階層で運送依頼が連鎖し、契約管理が複雑になりやすい構造があります。その結果、書面化が徹底されず、口頭や簡易なメールのみでのやり取りに留まってしまい、運賃や荷役条件が明確化されないばかりか、上位荷主から多段階ごとに中抜きが発生するため、実運送会社には適正運賃を大きく下回る運賃での取引を強いられることになります。
こうした状況を改善するためには、まずは元請(または荷主)が標準的な契約書式を用意し、下請企業にもそのフォーマットを使ってもらう仕組みが有効です。また、協力会社との覚書で「書面交付を必須化する」ルールを設定し、契約管理の姿勢を全体で統一することがポイントとなります。
中小企業が多いことで現場の実態把握が困難・アナログ慣習からの脱却
物流業界には中小・零細事業者が多数存在し、ITリテラシーや運用リソースに大きな差があります。FAXや口頭での契約になじんでいる企業が、いきなり電子契約システムを導入しようとしてもハードルが高いと感じてしまうのは当然かもしれません。
この課題を解決するには、「段階的なデジタル化」のアプローチが効果的です。まずは紙ベースでもよいので契約書面を確実に発行するルールを徹底し、その後にPDFやメール送付へ移行するなど少しずつデジタル化を進めます。最終的にクラウド管理や電子契約サービスを活用すれば、無理なくIT環境へ移行できるでしょう。
運送業者・荷主双方の協力体制の構築
書面化は運送会社だけで完結できるものではなく、荷主側の理解と協力も欠かせません。たとえば、発注書をきちんと発行したり、附帯業務が発生する場合は事前に通知したりするなど、日々の業務レベルで契約内容を明確にし、共有しておくことが重要です。
一部では「基本契約書を締結しておけば書面化対応として十分」といった見方もありますが、日時や荷役内容が毎回異なるような取引においては、運送案件ごとに発注書や運送申込書を交付し、具体的な運送条件を明記する運用が不可欠です。
特に、国交省が定めるKPI(荷待ち・荷役作業等の時間)を正確に把握・管理するためにも、「どの荷主の、どの案件で、どのような条件で運送が行われるのか」を明文化し、ドライバーが内容を確認・携行できる仕組みを整えることが望まれます。
定期的な案件で作業内容や時間指定が毎回同じ場合は基本契約でも運用可能ですが、案件ごとに条件が異なる場合は書面交付の運用が現実的かつ有効です。
書面化の具体的な進め方
![unsoukeiyakushomenka_03[1].jpg](../../../img/blog/images/unsoukeiyakushomenka_03%5B1%5D.jpg)
契約を文書化するための手順としては、まず既存のフローを見直し、その後デジタル化を活用する流れが一般的です。以下では、その取り組みについて順を追って解説します。
現行運用の見直し
はじめに、自社の契約フローを明確化することが重要です。どの段階で運賃や作業内容、日時などを決め、口頭・メール・FAXなどをどのように使い分けているかを洗い出したうえで、正式な契約書(運送申込書や運送引受書)をいつ、誰が発行すべきかをはっきりさせます。
また、国土交通省のガイドラインや標準貨物自動車運送約款などを参照しながら、運賃や附帯業務料、日時、支払方法といった記載事項が十分にカバーされているか検証し、不足している部分があれば補足すると良いでしょう。
デジタル化を活用した書面化の効率化
紙の契約書面を徹底する方法もありますが、電子契約やオンラインプラットフォームを使うことで業務効率を大幅に高める企業が増えています。書式テンプレートをあらかじめ用意し、WordやGoogleドキュメントで運送申込書・運送引受書を管理してPDF化し、相手に送付するだけでも押印やFAXの手間を削減できます。
さらに、電子契約サービスを導入すれば、合意のやりとりをクラウド上で完結し、契約内容の保管も一元管理できます。また、配車計画や運行管理と契約書面の作成を一元化できるクラウドシステムを合わせて導入すれば、二重入力や書面作成時のミスを減らし、請求から支払までのプロセスをシームレスにつなげられます。
運送申込書と運送引受書の適用方法
一般的な手順としては、荷主が運送申込書を発行し、それを受けた運送会社が運送引受書を返送する形が典型です。契約書面には、「貨物の品目や数量」「重量」「積み込み日時や場所」「荷卸し日時や場所」「運賃や料金の詳細(燃料サーチャージや有料道路代、附帯業務料を含む)」「支払条件」「トラブルが発生した際の責任分担」などを明示しておくと安心です。
作成した書面は、紙でも電子データでも最低1年間保管しなければならないため、メール送付のみに頼らず、システム上で一括管理できる環境を整えておくほうが紛失リスクを抑えられます。
荷待ち・荷役時間の削減のために納品伝票を電子化するなら invoiceAgent(インボイスエージェント)
運送契約のデジタル化と並行して、実際の現場でのやり取りもスムーズにしていくことが、書面化を本当の意味で機能させるポイントです。なかでも、納品伝票の電子化は、荷受け現場の準備をスムーズにし、結果的に荷待ち・荷役時間の削減につながる取り組みとして注目されています。
国土交通省をはじめとした経済産業省、農林水産省の3省合同で合議された「物流効率化に関する取りまとめ」では、荷主が講じるべき具体的な措置の一つとして「事前出荷情報の提供」が明記されており、その手段として納品伝票をデジタルデータで事前提供することが推奨されています。
この取り組みを支えるのが、ウイングアークが提供する電子帳票プラットフォーム「invoiceAgent(インボイスエージェント)」です。
invoiceAgentを活用すれば、既存の基幹システムを大きく変えることなく、紙の納品伝票をPDFやXML形式で出力・送信する仕組みを導入できます。これにより、着荷主(納品先)は納品前に情報を把握できるようになり、荷受け準備の効率化・荷待ち時間の削減に直結します。
![unsoukeiyakushomenka_05[1].jpeg](../../../img/blog/images/unsoukeiyakushomenka_05%5B1%5D.jpeg)
また、invoiceAgentで出力されるデータは「物流情報標準ガイドライン」に準拠しているため、他社の電子伝票システムともスムーズに連携が可能。物流現場の混乱を防ぎながら、標準化と効率化を同時に実現できるのも大きな特長です。
まとめ
2025年の法改正によって運送契約の書面化が強く求められる中、ドライバー不足や労働時間規制が進む業界では、従来のあいまいな契約慣習を続けるリスクがさらに高まっています。しかし、契約を明確にする作業そのものは決して難しくありません。書面化を徹底すれば、トラブル防止やコンプライアンス強化、適正運賃の確保、そして業務効率の向上と、企業にとって多くのメリットを生み出します。
まずは国土交通省のガイドラインに沿って運送申込書や運送引受書を導入し、クラウドプラットフォームや電子契約サービスを併用していくことで、書面化のハードルは大きく下がります。また、納品伝票や請求書など周辺帳票もあわせて電子化していくことで、現場のオペレーション全体を通じた業務効率化やトラブル防止につなげることができます。
今後の規制強化や業界変革に備え、早めに運送契約のデジタル化へ踏み出してみてはいかがでしょうか。導入に関するご相談も、ウイングアークにお気軽にお問い合わせください。