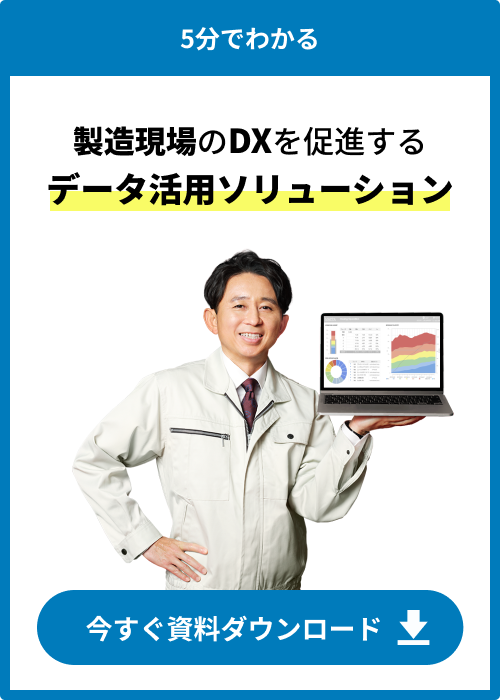工程管理とは
工程管理とは、どのようなことを指すのでしょうか。まず、製造業における工程管理とは何かを解説します。
製造業における工程管理
製造業における工程管理とは、現場での製造の進捗を把握し、問題なく作業が進むように行う管理のことです。
工程管理は生産計画と生産統制で構成され、製造現場における納期や品質、コスト、生産量の把握などに関わっています。
工程管理がうまくいかなければ、納期が遅れたり、品質が下がって廃棄が増えたり、在庫が多すぎてしまったりと、無駄が多くなってしまいます。
したがって工程管理は、生産工程を効率化するために実施されます。
生産管理との違い
工程管理と生産管理とでは、管理の範囲が異なります。
工程管理が、製造にあたっての計画や統制を示すものであるのに対し、生産管理はさらに広範囲にわたっての管理を示すものです。工程管理は生産管理のなかに含まれています。
生産管理では、工程管理よりもさらに前の段階にあたる需要の予測が行われ、予測結果を基に工程管理の基盤となる生産計画を立てていきます。さらに、製造の前には資材の仕入れ管理、製造の後には販売の管理といったことも生産管理に含まれます。
生産管理についてはこちらの記事で詳しく紹介しているので、あわせてお読みください。
製造業における工程管理の必要性

製造業における工程管理は、主に以下の観点から必要とされています。
- 納期を守るため
- 品質の確保、品質管理のため
- 生産リードタイム短縮のため
- 生産性の向上のため
- 人や設備の負荷調整のため
- 製造原価の低減のため
- 在庫削減効果のため
工程管理では、納期を守ることが大きな目的のひとつとなっています。顧客に対して、納期どおりに納品を行うことは、企業の信頼性を高め、将来的な販売の拡大にもつながるためです。
さらに余裕のある製造スケジュールを立てることで製品の品質を保ったり、不良品の削減や計画的な資材調達で製造原価を抑えたりすることも目的の1つです。
工程管理の必要性が増した背景
工程管理の必要性が増している背景には、企業活動に対するさまざまな要求が高まっていることが挙げられます。
とりわけ製造業に関しては、品質要件が厳しくなり、納期遅延が許されない時代が到来しました。わずかなコスト超過も、企業の利益に影響を与えるため避けなくてはなりません。
時代の流れでテレワークは増加していますが、これが損失につながらないよう、しっかりと管理を行う必要も出てきます。
工程管理を行い、現工程のスケジュールや進捗状況を把握することで、コスト増につながる問題点をより早く見つけ、改善策を施すことができるでしょう。
工程管理を行う方法

工程管理を行うためには、工程表を作成する必要があります。
その方法には、従来の管理方法と、最新システムを導入する方法があります。それぞれの方法について解説します。
ホワイトボードや紙面を使って管理する
ホワイトボードや紙面を使った管理は、アナログですがもっともオーソドックスな方法です。短期間のプロジェクトや、共有相手の少ない小規模な組織には向いているでしょう。
アナログでの管理は、現場で工程の変更や更新があったときに、すぐにその場で書き込み、共有できることがメリットです。コストも比較的安価で、工程を常に目視できるメリットもあります。
一方で、その場にいない人にはあらためて変更点を伝えなくてはならず、情報の共有が遅れる可能性があるのはデメリットでしょう。
エクセルで管理する
エクセルなどの表計算ソフトを使用して工程管理をする方法もあります。エクセルを工程管理に利用している企業は多いでしょう。
エクセルによる工程管理では、ガントチャートが一般的です。
ガントチャートとは棒グラフの一種で、日付をすべて横に並べたカレンダーのようなものです。縦軸には作業内容を並べ、作業が完成した割合に応じて色をつけるなどして、作業の完成度を可視化しています。
その他の工程表を使用する
工程表は、以下のような方法で作成することも可能です。
・横線式
横線式の工程表はガントチャートによく似ています。作業の完了率を示すガントチャートに対し、横線式は該当する期間に横線をひくことで工程を表します。
・曲線式
曲線式は、横に時間軸、縦に出来高の軸を取り、時系列にしたがって作業の進捗を可視化できる方法です。
・累計グラフ
累計グラフ式では、工期を区切り、工期内での作業の完成率をグラフ化して工程を管理します。
・ネットワーク式(ネットワーク図)
ネットワーク式の工程表は、作業の区切りを○、作業日数や作業内容を矢印で示す方法です。作業同士の関連性が見える一方、作成にも解読にも専門知識が必要になります。
工程管理システムで管理する
自社にあった形で工程管理ができるよう、専用の工程管理システムを構築、あるいは導入する企業も増えています。
工程管理システムでは、作業内容や進捗を簡単に可視化し、共有できるのがメリットです。
一方で、海外製品の中には可視化できても製造現場で活用しにくかったり、IT知識がなければ利用が難しいといったものもあるため、自社にあった方法を選ぶことが大切です。
工程管理がうまくいかないよくある課題
前述の方法で行うことが多い工程管理ですが、とりわけ以下のようなことが原因で、納期の遅れや品質劣化につながる兆候を見落とす可能性があります。
以下のような状態になっていないかチェックしましょう。
- 進捗状況をリアルタイムで把握できていない
- マネージャーやチームリーダーなど、一部の人間だけが進捗状況を把握している
- 外部との進捗状況の共有ができていない
- 部署間での情報の共有、一括管理ができていない
- 作業の偏りを可視化できず、仕事のできる人に作業が集中している
- 進捗報告に使うフォーマットがバラバラ
- 最新の進捗状況や成果物の確認に時間がかかりタイムラグが生じている
システム化により工程管理を効率化

工程管理は、工程管理システムの導入によって効率化することができます。どのように工程管理の効率化が実現するのか、具体的に説明していきます。
工程の可視化を実現する
工程管理システムによって、工程の可視化が実現します。工程の可視化とは、現在どの工程がどの程度進んでいるのか、次の工程は何で全体的にはどのような予定であるのかが、瞬時に見てわかるようになるということです。
工程が可視化すると、そのときの状況や予定について簡単に情報共有できるほか、トラブルに際しては素早く適切な対応が可能です。
人や設備の負荷が集中していないかどうか、常に確認をすることもできます。
品質や納期が守られ、生産性の向上にもつながる
工程管理システムによって、効率が悪い作業の有無がわかるようになるのもメリットです。
どの作業が効率を落としているかがわかれば、それを改善することで無駄を省き、重要な作業に時間をかけられるようになるでしょう。
したがって工程管理システムの導入は、工程管理の効率化に役立つだけでなく、作業そのものの効率化も導きます。
作業に余裕が生まれると高い品質の保持が可能になり、納期も守られるなど、生産性の向上につながります。
全社で状況を共有でき、スケジュール調整しやすくなる
工程管理システムを導入すると、たとえ拠点が離れていてもリアルタイムに情報共有が可能となります。それまでに行っていた、スケジュールなどに関する連絡、報告、集計などの作業は不要となり、調整もしやすくなるでしょう。
工程の遅れやトラブルに関しても同様です。担当者が工程管理システムを入力すれば、管理者がリアルタイムで状況を把握できるため、素早くリカバリーに向けて動き出すことが可能です。工程管理そのものの手間が省かれ、効率化が実現できます。
工程管理の手順

工程管理の手順では、PDCAサイクルを繰り返し回すことが重要です。
PDCAサイクルとは、P(Plan:計画立案)→D(Do:実行)→C(Check:評価)→A(Action:改善)の4つを示します。Aを行ったらまたPに戻り、繰り返すことからPDCAサイクルと呼ばれています。
PDCAサイクルを用いた工程管理の手順について、以下で詳しく説明します。
1.【Plan】工程管理の計画を立てる
工程管理をはじめるときは、最初に適切な生産計画を立てましょう。生産計画とは、いつまでに、どれくらいの作業をどこまで進めるのか、何をどれだけ生産するのか、という計画です。
ただし作業量や時間、生産量だけを決めれば良いのではなく、それにかかるコストや設備、人員の確保も考慮しなくてはなりません。こうした生産計画を元に、各工程の全体像を把握し、工程の計画を立てます。
2.【Do】工程管理を実施する
工程管理の計画ができたら、計画を実行します。つまり、計画どおりの工程管理を進めていきます。
実施する工程は、必ず経過を観測しなくてはなりません。現在の状況を正確に把握し、どこで、どのような問題が発生したか、モニタリングし続けましょう。
3.【Check】工程管理の成果を評価する
実際に工程管理を行った結果、計画どおりに生産できているかを確認します。もしも問題が生じている場合は、原因究明を行いましょう。
Checkの重要な部分は、計画と実際の工程に差異がないかどうか、ある場合はどれくらいの差異があるのかを確認するところです。問題や差異を突き詰め、改善方法を探ります。
4.【Action】工程管理の問題点を改善する
工程管理の成果評価によって改善の方法が明らかになったところで、問題を解決するために改善方法を実施します。
Actionは改善の実施段階ですが、改善を実施したところで終わりではなく、Actionの結果を受けて新たなPlanを立て、実行しなければなりません。PDCAを回して改善を繰り返すことで、工程管理の精度を高めていくことができます。
製造業における工程管理で注意すべきこと

とりわけ製造業において留意したい、工程管理の注意点を解説します。
複数のプロジェクトが進行している場合は工程管理システムを活用する
複数のプロジェクトが同時に進んでいる場合は、横断管理が必要になります。その際、人力での把握には限界があるため、工程管理システムの活用がおすすめです。
とりわけ大規模なプロジェクトになるほど、効率の良い工程管理が求められます。製品の品質にも影響を及ぼすため、システムの導入はプロジェクトの成功を左右する要素です。
納期だけでなく、リスク管理をしっかりする
価値の高い製品を作るためには、納期にばかり着目しないように注意することも重要です。工程管理を行う際は、人、設備、品質、リスクなどを管理する必要があります。
たとえば、特定の作業員や作業ラインへの負荷の偏りはリスクを高めるため、負荷の偏りが生じないようにしなくてはなりません。このため工程管理では、負荷の状況も「見える化」する必要があります。
他システムとの連携も重要
工程管理と他システムとの連携により、あらゆるニーズへの対応が可能となります。工程管理システムの導入時に、既に利用しているシステムと連携できるものを選択すると、効率が良いでしょう。
たとえば、生産管理や在庫管理システムとの連携により、資材の必要量、現在の在庫数、今後の見通しなども確認できます。一括管理が可能になると、AIやIoTを活用して自動化技術を取り入れた工場「スマートファクトリー」など、製造業のDX化に対しても可能性が広がります。
まとめ
工程管理は、企業が高品質な製品を製造し、企業価値を高めるためには必要不可欠です。
PDCAを回しながら常に改善方法を探り、運用していくことが求められますが、さらに効率的な工程管理を行うためには、まずは工程の可視化に取り組むことがおすすめです。
ウイングアークが提供する「MotionBoard」は、さまざまな生産工程のデータを集約しリアルタイムで可視化することができるソリューションです。
従来の紙媒体やエクセルによる工程管理では実現できなかった情報の伝達、共有、製造現場の状況把握が可能となります。
工程管理の可視化をご検討の際には、お気軽にご相談ください。