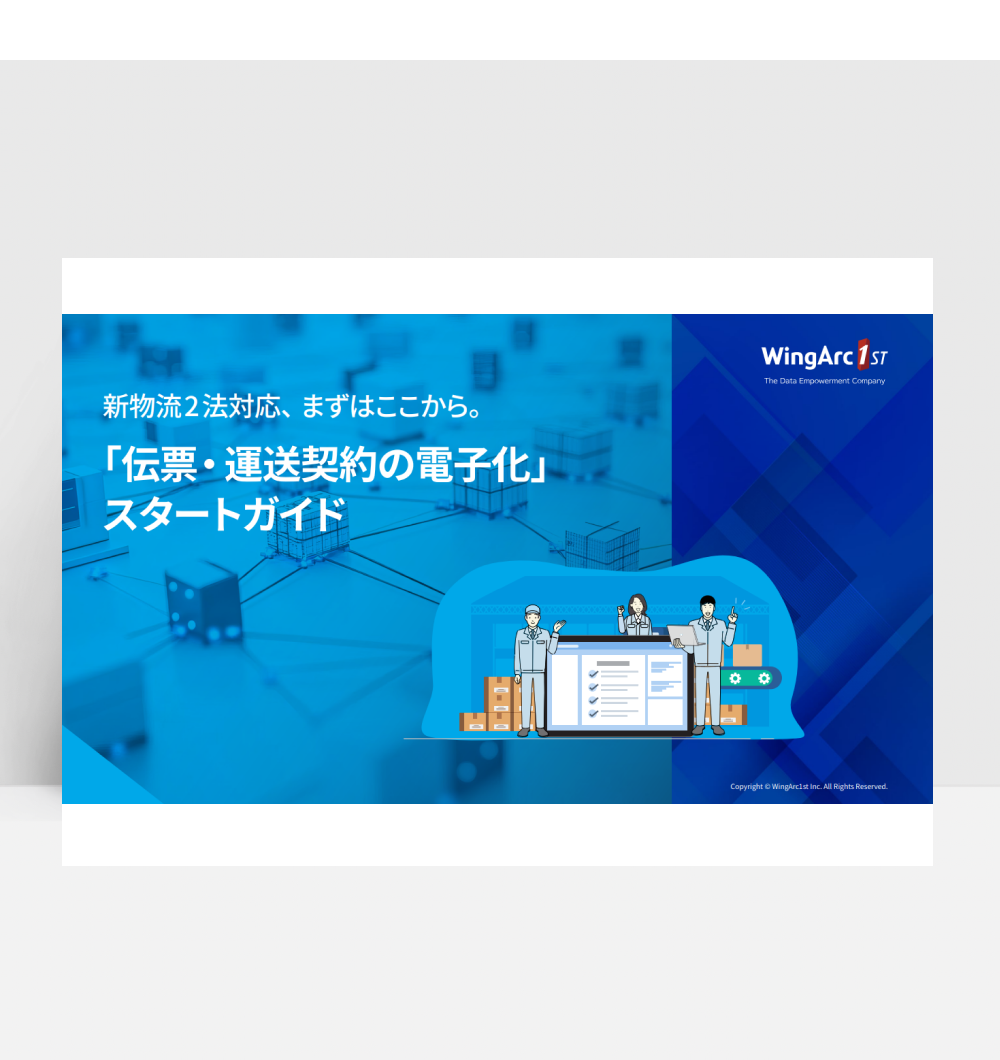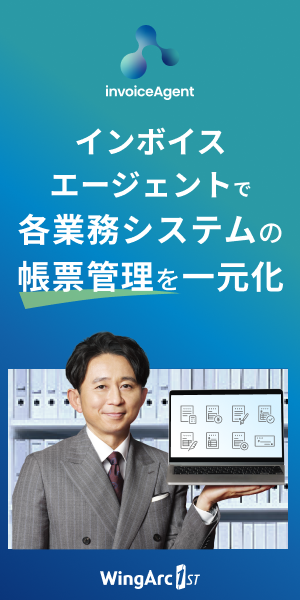CLO(物流統括管理者)とは?
物流統括管理者(CLO:Chief Logistics Officer)は、企業の物流戦略を一元管理し、サプライチェーン全体の最適化を推進する役職です。
欧米では既にCEO(最高経営責任者)やCFO(最高財務責任者)と並ぶ役員クラスとして定着しており、ウォルマートではCLO(物流統括管理者)が経営の重要ポジションを担うなど、多くの企業でCSCO(最高サプライチェーン責任者)が経営の中核に据えられる事例が増えています。
一方、日本においては、物流管理が部門単位で行われるケースが多く、経営戦略と現場の物流施策との間にギャップが生じることが課題でした。しかし、2026年4月からの法改正によって、年間貨物取扱量が9万トン以上の特定荷主にはCLOの選任が義務付けられます。
従来の「物流部長」や「SCM(サプライチェーン・マネジメント)担当」と異なり、CLOは調達・生産・販売など各部門を横断しながら社内外の物流改革をリードする立場として、企業経営に深く関与することが求められます。
「物流統括管理者(CLO)」の選任が義務化される背景
日本の物流業界では、ドライバー不足や多重下請構造、そして2024年問題による輸送力低下が深刻な課題です。
国土交通省が示す「2024年以降のトラックドライバー不足」は、企業の物流戦略そのものの抜本的な見直しを迫るものであり、従来のように運送会社任せでは十分な対応が難しくなっています。さらに、現場には電話やFAX、紙帳票などアナログな商習慣が根強く、情報連携の遅れが荷待ち時間や積載率低下を招いているのが現状です。
こうした問題を解決するため、特定荷主にも物流効率化の責任を負わせ、「経営レベルでのサプライチェーン最適化を推進しよう」というのが政府の狙いです。
CLOは調達から販売までのプロセスを横断的に管理し、データを活用しながら施策を主導する立場として位置付けられています。物流をコストセンターではなく、競争力を生み出す戦略領域と捉え、企業成長につなげるためにも、CLOの存在が今後ますます重要になっていくでしょう。
CLOが担う役割と具体的な数値目標

物流統括管理者(CLO)には、企業の物流戦略を経営視点で推進しながら、サプライチェーン全体を最適化へ導くことが期待されています。
具体的にどのような業務や目標を担うのか、以下で見ていきましょう。
特定荷主における中長期計画の策定・提出
物流統括管理者(CLO)がまず取り組むべき業務の一つとして挙げられるのが、特定荷主に義務付けられる「中長期計画」の策定です。
前年度に年間9万トン以上の貨物を扱う荷主企業は、2026年4月までにCLOを選任し、荷待ち・荷役時間の削減や積載率向上などを盛り込んだ計画書を国に提出する必要があります。これは改正物流関連2法の趣旨に沿って、荷主企業にも輸送効率化の責任を負わせようとする国土交通省の方針に基づくものです。
CLOは、この中長期計画を単なる書面上の義務ではなく、社内外の調整役として戦略的に活用することが求められます。
生産計画や販売戦略、さらには運送契約や倉庫オペレーションのデジタル化など、多角的な施策を総合的に企画・実行するのがポイントです。たとえば、「車両手配を一元管理できる仕組みを導入する」「荷受け先と連携してトラックの待機時間を減らす」「共同輸配送を検討する」など、具体的な改善ステップを設定していきます。
荷待ち・荷役時間の削減(年間125時間/人の短縮)
国土交通省や経済産業省が掲げる中長期目標の一つとして、「ドライバー1人あたり年間125時間の荷待ち・荷役時間削減する」というものがあります。この目標は、現状では1運行あたり3時間以上かかっている荷待ち・荷役作業を、全体の5割の運行で合計2時間以内に収めることを目安とした取り組みです。
背景には、発荷主・着荷主・物流事業者がそれぞれ自社の都合を優先してきた従来の商習慣が、無駄な待機時間や非効率を生み出してきたという構造的な課題があります。なかでも、ドライバーが無償で積み降ろし作業を行う「自主荷役」の慣習は、長時間労働の温床とされており、今回の新物流2法では、荷役作業に対価を支払うか、パレット化などによって荷役の効率化を図るかのいずれかを選択し、抜本的な改善を求める方針が示されています。
物流統括管理者(CLO)は、この目標を実現するうえで重要な立場にあります。たとえば、生産側の都合で在庫確保をギリギリまで遅らせる運用が着荷先の荷役スケジュールに影響する場合、CLOが主体となり発注ロットの見直しや事前情報の共有ルールを整備するなど、根本的な仕組みを変えていく必要があります。
この取り組みによって、ドライバーの稼働効率を高め、企業全体の運送コスト最適化につなげられます。
積載率16%向上による輸送能力の拡大
もう一つの目標となるのが、「積載率を高めて輸送能力を16%増やす取り組み」です。トラック1台あたりの積載効率が上がれば、同じリソースでより多くの貨物を運べるため、ドライバー不足への対処やコスト削減に直結します。
ただし、大きく積載率を上げるには、共同輸配送やモーダルシフトなど根本的な改革が不可欠です。CLOは社内外の物流データを分析し、ピーク時の荷量分散や配送スケジュールの再構築など、戦略的な調整を行う必要があります。
具体的には、小売店への納品が特定の曜日に集中しないよう平準化したり、工場出荷と卸・小売への配送タイミングを一括管理したりするなどのアプローチが考えられます。
全社・業界横断の物流改革
こうした大幅な効率化には、従来の管理体制だけでは限界があります。CLOが経営視点のリーダーシップを発揮し、サプライチェーン上のあらゆる関係者を巻き込むことが重要です。生産・販売部門との協議や需要予測との連動に加え、業界全体で共同配送を模索するなど、大規模な取り組みが期待されます。
政府が掲げるKPIを達成するだけでなく、企業としても在庫コストの削減やリードタイム短縮、CO₂排出量の低減など幅広いメリットを享受できます。
CLOはデジタル技術を活用しつつ、このような改革を社内外に示す責任を負う存在です。
CLO成功のカギは「デジタル化」
物流統括管理者(CLO)はサプライチェーン全体の課題を洗い出し、政府が掲げる数値目標や中長期計画を実行に移す責務を負います。そのためには、全社的な物流戦略の見直しと具体的な施策推進が求められます。
しかし、従来のアナログ管理では、これらのミッションを的確かつスピーディーに遂行することは困難です。CLOの活動を成功に導くカギは「現場データの可視化」と「即応性」にあり、これを支えるのがデジタル化です。
ここでは、まずアナログ管理の限界について見ていきましょう。
アナログ管理の限界
現在も多くの物流現場では、電話・FAX・紙帳票といったアナログな手段が業務の中心となっています。
たとえば、配車の依頼を電話で行い、伝票は手渡しや郵送でやり取りする、というような手法です。
こうしたアナログ運用には以下のような問題が潜んでいます。
現場状況がリアルタイムで把握できない
どの程度の荷待ち・荷役時間が発生しているかなど、現場で何が起きているかを即時に確認できなければ、軌道修正や対策が後手に回ります。
また、多重下請構造により、どの運送会社・ドライバーが実際に来るのかが分からないケースも多く、情報の不透明さが可視化の障壁となっています。
データが分散し、分析に手間と時間がかかる
紙やExcelで個別管理された情報は統合が難しく、分析・報告にも膨大な時間を要します。経営層へのレポート作成や国への提出資料作成も非効率です。
さらに、新物流2法に基づく中長期計画の策定や数値目標の管理には、荷待ち・荷役時間、積載効率などのデータを取得・集約する必要がありますが、これらの情報は多段階の末端運送会社のドライバーや荷卸し先の現場にまたがっており、企業間を越えた情報共有が前提となります。
報告・収集の手段がアナログのままでは、必要なデータの取得に大きな労力と時間がかかることが避けられません。
属人化とヒューマンエラーのリスクが高い
担当者の経験や勘に依存した業務は、業務継続性や精度にばらつきが出やすく、CLOが全体を俯瞰してマネジメントするには不向きです。
こうした課題は、計画立案時点では見えにくくても、運用フェーズで確実に足かせになります。
逆に言えば、CLOが成果を出すためには、業務の根幹にある情報の取得・共有・活用のプロセスをデジタル化することが必須条件だといえるでしょう。
CLOが取り組むべきデジタル化のポイント
アナログ管理における課題を解決し、CLOが求められる中長期計画の実行において重要となるのが、契約・配車・運行といった情報をクラウド上で一元管理できる「物流DX基盤(物流情報の統合管理プラットフォーム)」の整備です。
荷主・運送会社・ドライバーなど関係者がオンラインで情報を共有できる仕組みを構築することで、紙の契約書や電話・FAX中心のやり取りから脱却でき、情報共有のスピード向上や転記ミスの削減につながります。
また、荷待ち・荷役時間や配送状況などのデータをリアルタイムで可視化できれば、中長期計画とのギャップ把握や改善策の立案が迅速になります。
まとめ
2026年4月から特定荷主に対して物流統括管理者(CLO)の選任が義務化され、物流業界は大きな転換点を迎えます。これまで現場任せだった部分的な改善にとどまらず、経営レベルの視点でサプライチェーン全体を見直す取り組みが、いっそう重要になるでしょう。
CLOは、単なる物流部門の管理者ではなく、調達・生産・販売など複数部門を横断しながら、国土交通省が示す「年間125時間/人の荷待ち」「荷役時間削減や積載率16%向上」といった大胆な目標を現実に落とし込む役割を担います。しかし、アナログ業務フローのままでは、計画の実行や進捗管理に大きな制約が生じてしまいます。
そこで、クラウド型の物流管理システムやデジタルツールを活用し、契約管理・運行管理・現場データの収集などを効率化することで、CLOが掲げる施策と現場オペレーションを連動させることが可能です。
CLOの選任とデジタル化の推進を同時に進めて、時代が求める大改革をスピーディーに実現していきましょう。