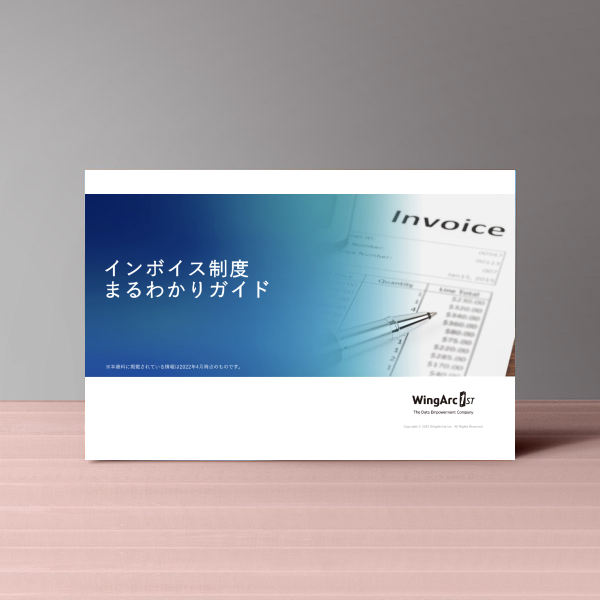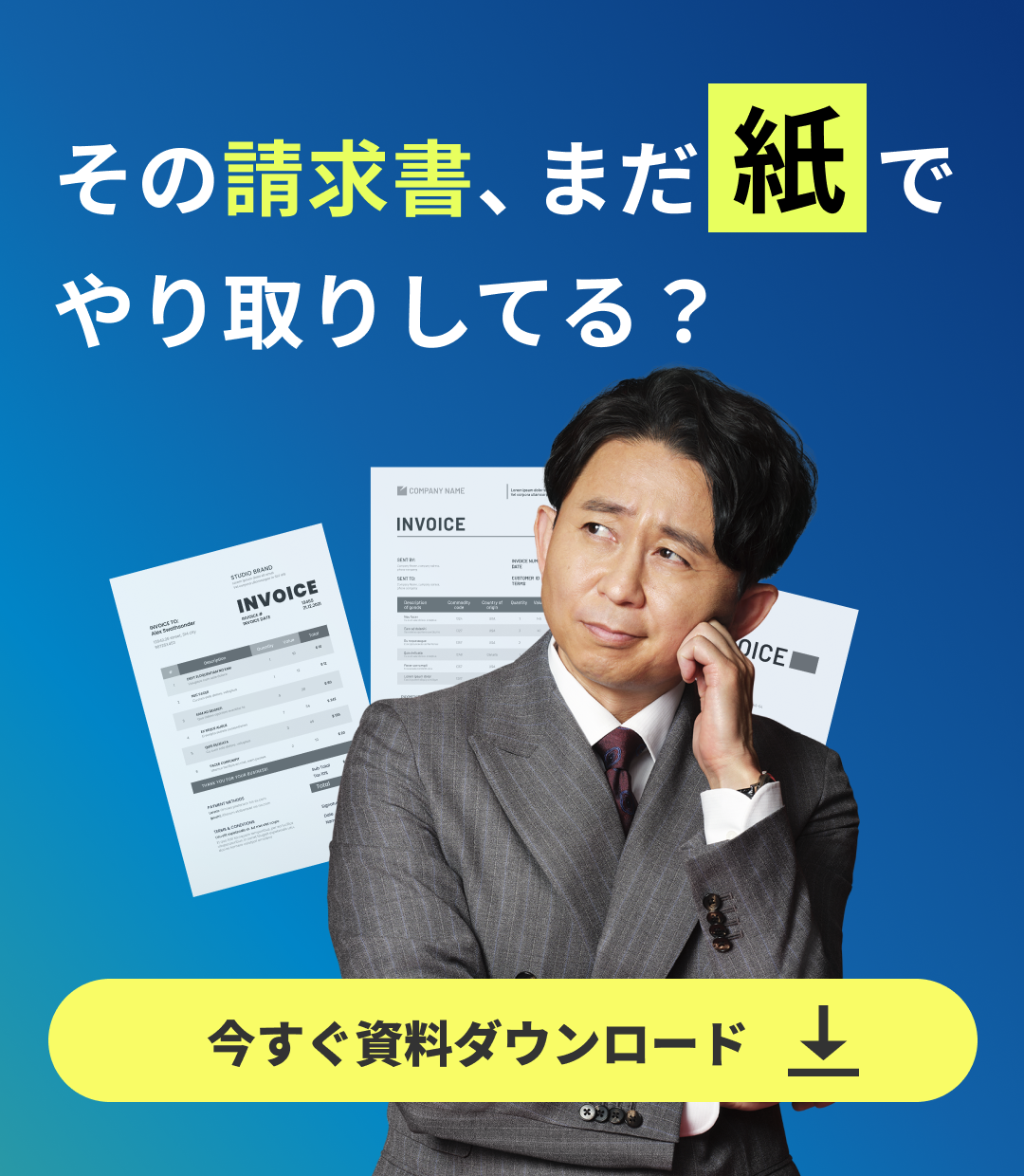そもそもインボイス制度とは?
まずは、インボイス制度とはどのような制度なのかを確認しておきましょう。
インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関する新制度で、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイス制度が開始した2023年10月1日以降、消費税の仕入税額控除を受けるには、適格請求書(通称:インボイス)の適正保存が必要になります。
そして、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に登録申請した課税事業者のみであり、免税事業者からの仕入税額は原則として控除できなくなります。
そのため、免税事業者においては「課税事業者になるか否か」の判断を、課税事業者においては「免税事業者との取引を継続するか否か」の判断を迫られている状況だと言えます。
インボイス制度が建設業に及ぼす影響とは?

インボイス制度の開始により、建設業の受発注にも大きな影響が及ぶと考えられています。
その理由として、建設業界特有と言える「一人親方」の存在があります。
次は、インボイス制度が建設業界に与える影響を見ていきましょう。
一人親方への発注に影響
建設業では、一人親方に業務を発注するケースが多々あります。
国土交通省が2020年に公開した資料によれば、建設技能者のうち15.6%は一人親方であり、その数は約51万人にのぼると示されています。
(参照:建設市場整備:建設業の一人親方問題に関する検討会 - 国土交通省)
そして、一人親方の多くは免税事業者であり、インボイス制度開始後の消費税額控除で必要になる適格請求書を発行することができません。
発注側の企業としては、一人親方からの仕入税額控除が適用されず、従来よりも税負担が大きくなってしまいます。
そのためインボイス制度の開始後は、一人親方への発注が敬遠されるケースや、消費税分の値引きを要求されてしまうケースが予想されます。
偽装請負の是正
インボイス制度の開始により、建設業界で深刻な問題となっている「偽装請負」の是正につながるという意見もあります。
偽装請負とは、各種保険料や法的福利費などの支出を抑えるため、建設会社が従業員に対して独立を促し、一人親方として今まで通りの業務を請け負わせることを指します。
インボイス制度の開始後は、免税事業者の一人親方からの仕入税額を控除できなくなるため、偽装請負を行うことの旨味が少なくなると考えられています。
建設業のインボイス制度対応のポイント
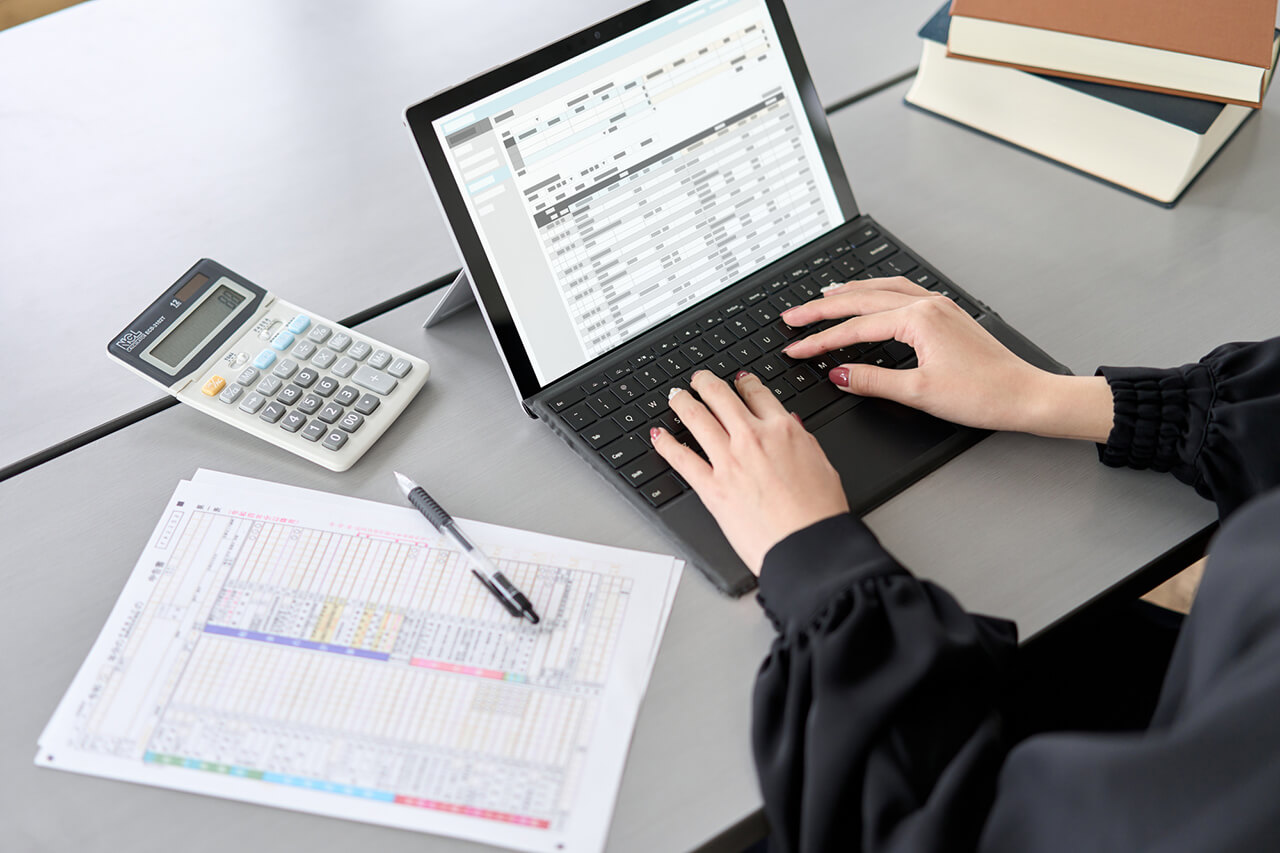
次は、一人親方などの受注者側の立場、そして発注者側の立場から、インボイス制度における対応のポイントをそれぞれ確認していきましょう。
受注者側の準備・対応
一人親方などの受注者側の準備・対応として、適格請求書発行事業者になるか否かを判断する必要があります。
インボイス制度の開始後、適格請求書を発行できないことで発注先の候補から外されてしまうケースが考えられるため、早い段階で適格請求書発行事業者の登録申請を行うことをおすすめします。
とはいえ、免税事業者から課税事業者に切り替えるのは、納税に関する事務処理の負担から難しいと考える一人親方も多いことでしょう。
そのような場合、簡易課税制度や2割特例を利用することで、インボイス制度開始後の事務処理負担を軽減できるかもしれません。
簡易課税制度とは?
簡易課税制度とは、個人事業主や中小事業者の事務処理負担軽減を目的とした特例制度で、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が利用できます。
通常、消費税の納税額は「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入等に係る消費税額」を差し引いて算出しますが、簡易課税制度を適用する場合は以下のように「みなし仕入率」を利用して納税額を算出します。
消費税の納税額=「課税売上に係る消費税額」-(「課税売上に係る消費税額」×「 みなし仕入率」)
なお、事業区分によって「みなし仕入率」は異なり、建設業の「みなし仕入率」は70%に設定されています。
課税売上に係る消費税額さえ把握していれば納税額を算出できるため、リソースに限りがある一人親方でも対応しやすいでしょう。
2割特例とは?
2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は「2割特例」を利用することができます。
「2割特例」は、免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するための特例措置で、売上税額の2割を納税額とすることができる制度です。
売上・収入を把握するだけで税額を算出・申請することができるため、事務処理にリソースを割きづらい一人親方であっても、簡単に税金の申告を行うことができるでしょう。
発注者側の準備・対応
一人親方などに発注する側の対応としては、発注先の事業者が適格請求書発行事業者に登録済みかどうかを確認する必要があります。
発注先が免税事業者、あるいは課税事業者でも適格請求書発行事業者の登録を受けていない場合、消費税額の負担が大きくなってしまいます。
2023年10月から6年間は経過措置が適用されるとは言え、控除割合は限定的かつ段階的に引き下げられる予定となっています。
「いつまで免税事業者への発注を継続するか」という点を明確にし、取引のある一人親方に対して、課税事業者への切り替えおよび適格請求書発行事業者の登録を依頼しましょう。
また、取引先の意向によっては、発注先の見直しも検討する必要があると言えるでしょう。
インボイス制度への対応なら「invoiceAgent」

インボイス制度の開始後は、納税に関する事務処理の負担増加が見込まれるほか、従来よりも請求業務が煩雑化すると言われています。
そのため、インボイス制度に向けた準備と並行して、請求業務のデジタル化・効率化に着手することをおすすめします。
次は、インボイス制度への対応および請求業務の電子化を実現するソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent 電子取引(インボイスエージェント電子取引)」を紹介します。
送受信の電子化で請求業務を効率化
「invoiceAgent 電子取引」は、請求書などの企業間取引文書の送受信を電子化するソリューションです。
PDFファイルをアップロードするだけで請求書をWeb配信でき、取引先から発行される帳票も「invoiceAgent 電子取引」を介して受け取ることができます。
また、CSVファイルの請求データを所定のフォルダにアップロードすることで、PDFファイルとして自動出力することも可能です。
これらの特徴により、紙ベースの作業よりも正確かつ効率的に請求書発行業務を進められるでしょう。
また、オプションの郵送サービスを利用すれば、Web配信と郵送のハイブリッド運用を実現することも可能です。
インボイス制度に対応する機能が充実
ウイングアーク1stはデジタル庁認定のPeppolサービスプロバイダーであり、「invoiceAgent 電子取引」はデジタルインボイス(電子化した適格請求書)の標準仕様である「Peppol」に対応しています。
「invoiceAgent」単独でPeppolに対応可能で、既存の業務システムがPeppolに対応していなくても、Peppolフォーマットへの変換やPeppolネットワーク経由のデータ送受信を行えます。
また、紙で受領した適格請求書のデータ化や、適格請求書発行事業者の登録番号確認(※)も「invoiceAgent」で行うことが可能です。(※アップデート予定)
電子帳簿保存法への対応も万全
請求書を電子データとして保存する場合、電子帳簿保存法への対応が必要です。
「invoiceAgent 電子取引」は、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトウェアの証である「JIIMA認証」を取得しています。
電子帳簿保存法の要件に対応する機能を備えているため、請求書を送る側も受け取る側も電子帳簿保存法に対応できます。
まとめ
今回は、インボイス制度が建設業界に及ぼす影響や対応のポイントを解説しました。
建設業界においては、一人親方として建設業に従事している個人事業主の方や、一人親方に発注している建設会社は多いことでしょう。
インボイス制度の開始に伴い、免税事業者の一人親方は「課税事業者になるか否か」の判断をしなければならず、一人親方との取引がある建設会社も発注先の見直しなどを検討する必要があります。
また、インボイス制度の開始後は、納税に関する事務処理だけでなく、請求書関連の業務負担も増加すると考えられています。
そのため、インボイス制度に向けた準備に加えて、請求業務を効率化する取り組みも重要になります。
今回ご紹介した情報も参考に、請求業務の電子化とインボイス制度への対応を実現する「invoiceAgent」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。