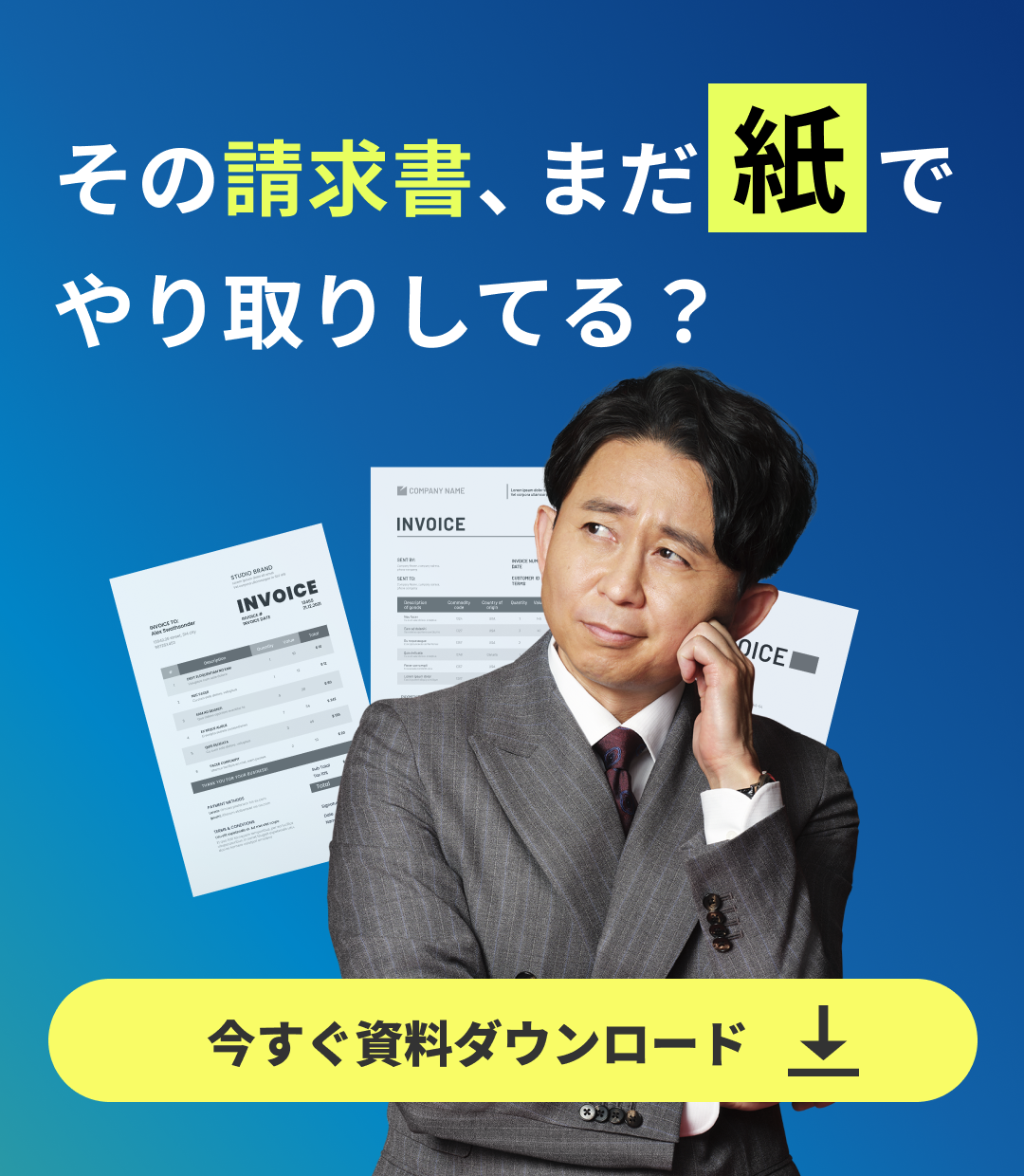インボイス制度における領収書の扱い

まずは、インボイス制度の概要について簡単におさらいするとともに、インボイス制度における領収書の扱いを確認していきましょう。
そもそもインボイス制度とは仕入税額控除に関する新制度のことで、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。
2023年10月1日のインボイス制度開始以降、仕入税額控除を受けるには「適格請求書(通称:インボイス)」の適正保存が必要になります。
適格請求書とは、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類であり、記載事項に一定の要件があります。
「適格請求書」という言葉から「請求書のみが該当する」と思われがちですが、「領収書」や「レシート」であっても適格請求書に該当する可能性があります。
つまり、仕入先から受け取る領収書で仕入税額控除を受けたい場合には、適格請求書の要件を満たす領収書を受領・保存する必要があります。
また、適格請求書の要件を満たす領収書を保存していれば、別途請求書を受領・保存しなくても仕入税額控除を受けることができます。
インボイス制度における領収書の基本ルール

次は、インボイス制度の開始に伴い覚えておきたい、領収書に関するルールを紹介します。
- 記載事項の変更が必要
- 簡易インボイスを交付できる事業者も
- 3万円未満の取引でも領収書が必要に
記載事項の変更が必要
領収書を適格請求書として発行するのであれば、適格請求書の要件を満たすフォーマットに変更する必要があります。
具体的には、適格請求書には以下の記載事項が必要です。
(1)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごとに合計した対価の額および適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
簡易インボイスを交付できる事業者も
不特定多数の顧客に対応する小売業や飲食店業、タクシー業などの事業者の場合、領収書・レシートを発行するたびに「(1)書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」を確認して記載するのは現実的とは言えません。
そのため、不特定多数の者に対して販売等を行う一部の事業者に関しては、適格請求書の記載事項を簡易化した「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の交付が認められています。
適格簡易請求書の記載事項は以下の通りです。
(1)取引年月日
(2)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(3)税率ごとに合計した対価の額
(4)税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
(5)適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
3万円未満の取引でも領収書が必要に
現行制度では、税込み3万円未満の取引に関して、記載条件を満たした帳簿さえあれば領収書やレシートがなくても仕入税額控除が適用されていました。
しかしインボイス制度においては、3万円未満の取引に関しても、控除を受けるには適格請求書(もしくは適格簡易請求書)の要件を満たす領収書・レシートが必要になります。
適格請求書発行事業者は、取引先からの求めに応じて適格請求書を発行する義務があるため、取引金額が3万円未満であっても領収書を発行できるよう準備しておく必要があります。
なお、令和5年度税制改正で少額特例が設けられたことで、2023年10月から2029年9月末までの間に日本国内で行った税込み1万円未満の課税仕入れについて、適格請求書などの保存がなくても、一定の記載をした帳簿の保存があれば仕入税額控除を受けられることとなりました。
適格請求書の電子化を検討すべき理由

領収書やレシートであっても要件さえ満たせば適格請求書に該当するとお伝えしましたが、その適格請求書の電子化を検討する企業が増えつつあります。
次は、適格請求書の電子化を検討すべき理由を見ていきましょう。
領収書や請求書に関する処理が煩雑化
適格請求書の電子化が注目を集める最大の理由が、インボイス制度開始後の業務負担増加です。
インボイス制度の開始後は、発行・受領した領収書や請求書が適格請求書の要件を満たしているかどうかを確認する必要があり、適格請求書とそれ以外を仕分ける手間も発生します。
そのため、今まで以上に領収書や請求書に関する処理が煩雑化し、担当部門の業務負担が増加すると考えられているのです。
そうしたなか、社会的システム・デジタル化研究会は2020年に「社会的システムのデジタル化による再構築に向けた提言」を公表し、インボイス制度の開始に際して当初から電子インボイス(電子化した適格請求書)を前提とした業務プロセスを構築すべきという考えを示しました。
適格請求書を電子化、つまり電子インボイスに切り替えることで、人手よりも効率的に領収書や請求書を処理することが可能になり、インボイス制度開始後の業務負担を軽減につなげることができるでしょう。
「Peppol(ペポル)」の普及・促進
デジタルインボイスを普及・促進するための動きも活発化しています。
社会的システム・デジタル化研究会の下部組織である「デジタルインボイス推進協議会(EIPA)」は、国内におけるデジタルインボイスの標準仕様を「Peppol」に準拠することを発表し、日本版Peppolと言える「JP PINT」を策定しました。
また、デジタル庁も「デジタルインボイスの標準仕様の普及等」を政策のひとつに掲げており、日本版Peppol「JP PINT」の普及促進を官民一体の重大プロジェクトに位置づけています。
デジタル庁は2021年9月に「Peppol」を管理する国際非営利組織「OpenPeppol」の正式メンバーとなりました。
日本の管理局(Japan Peppol Authority)として、Peppolサービスを提供できる事業者「Peppolサービスプロバイダー(Peppol Service Provider)」の認定手続きを開始しており、現在(2023年10月時点)は33の事業者が日本におけるPeppolサービスプロバイダーとして認定されています。
(参照:JP PINT|デジタル庁)
4社に1社がPeppolを用いた商取引に対応予定
デジタル庁認定のPeppolサービスプロバイダーであるウイングアーク1stが2022年12月に行った「インボイス制度対応状況に関する調査」によれば、アンケート対象となった企業の24.6%が「Peppolを用いた商取引に対応予定」、20.0%が「検討中」と回答。
すでに約4社に1社がPeppolに対応する意向を示しており、Peppolを用いた商取引に対応する企業は今後ますます増えていくと予想されます。
<調査概要>
- 調査名:インボイス制度に向けた企業間取引の電子化に関する対策調査
- 有効対象:100億円以上の売上の企業に所属する請求書関連業務に携わる会社員
- 有効回答数:500名(建設業101名、製造業104名、情報システム・ソフトウェア業103名、金融・保険業104名、卸売り・小売業88名)
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。 - 調査期間:2022年12月2日〜同年12月6日
▼調査の詳細はこちら
大企業を中心としたインボイス制度対策状況を調査 インボイス制度対応中は41.0%に上昇、財務経理部門と情シス・DX推進部門間連携は3ヶ月半で約20%加速 | ウイングアーク1stコーポレートサイト
インボイス制度への対応なら「invoiceAgent」
次は、インボイス制度に対応する具体的なソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent(インボイスエージェント)」を紹介します。
適格請求書の送受信を電子化する「invoiceAgent 電子取引」
「invoiceAgent 電子取引」は、請求書や領収書などの企業間取引文書の送受信を電子化するソリューションです。
PDF形式の文書データを「invoiceAgent 電子取引」にアップロードするだけで、取引先に配信することができます。
また、「invoiceAgent 電子取引」はインボイス制度への対応という面でも有効です。
「Peppol」経由のデータ送受信に対応予定で、受領した適格請求書のデータ化や、登録番号の照合も「invoiceAgent 電子取引」上で対応可能です。
紙の適格請求書をデータ化する「invoiceAgent AI OCR」
「invoiceAgent AI OCR」は、紙の適格請求書をデータ化するソリューションです。
「invoiceAgent AI OCR」には、特徴の異なる5つのOCR/AI OCRエンジンが搭載されています。
データ化する文書の種類や特徴に応じて適切なエンジンを選択したり、1つの読み取り項目に対して複数のエンジンで処理を実行したりすることも可能です。
また、読み取り画像の歪みや傾きを自動で補正する機能も備わっており、認識率の低下を防ぎます。
これらの特徴により、活字・手書きを問わず領収書などの適格請求書をデータ化することが可能です。
文書管理の一元化なら「invoiceAgent 文書管理」
「invoiceAgent 文書管理」は、文書管理の一元化を実現するソリューションです。
「invoiceAgent」で作成・出力した文書データはもちろん、他システムで出力した文書データもまとめて取り込み、ルールに従って自動で仕分け・保存を実行します。
保存した文書データは、複雑な条件にも対応する検索機能によって速やかに参照することが可能です。
また、保存期間に応じた自動削除機能や証跡管理機能も備わっているので、安全かつ効率的に文書管理を行うことができます。
まとめ
今回は、インボイス制度における領収書の扱いやルール、適格請求書の電子化が注目を集める理由などを解説してきました。
インボイス制度の開始により、一定の記載事項を満たしていれば領収書やレシートも適格請求書として扱うことができます。
そして、インボイス制度開始における業務負担を軽減するには、適格請求書の電子化が有効です。
今回ご紹介した情報も参考に、「invoiceAgent」でインボイス制度に向けた準備を進めてみてはいかがでしょうか。