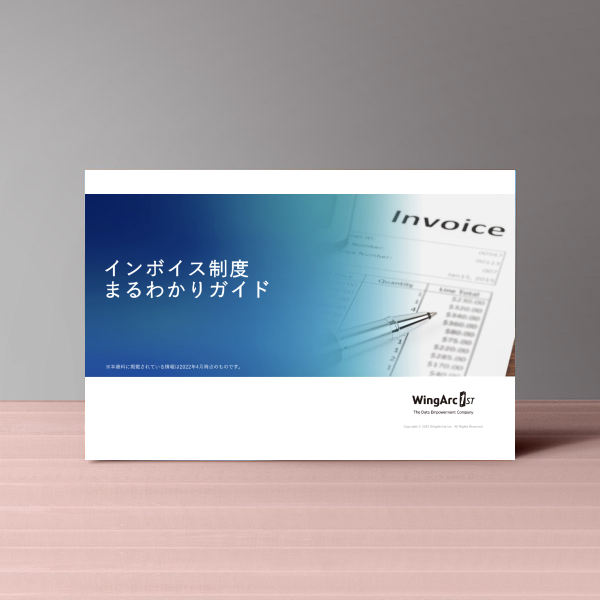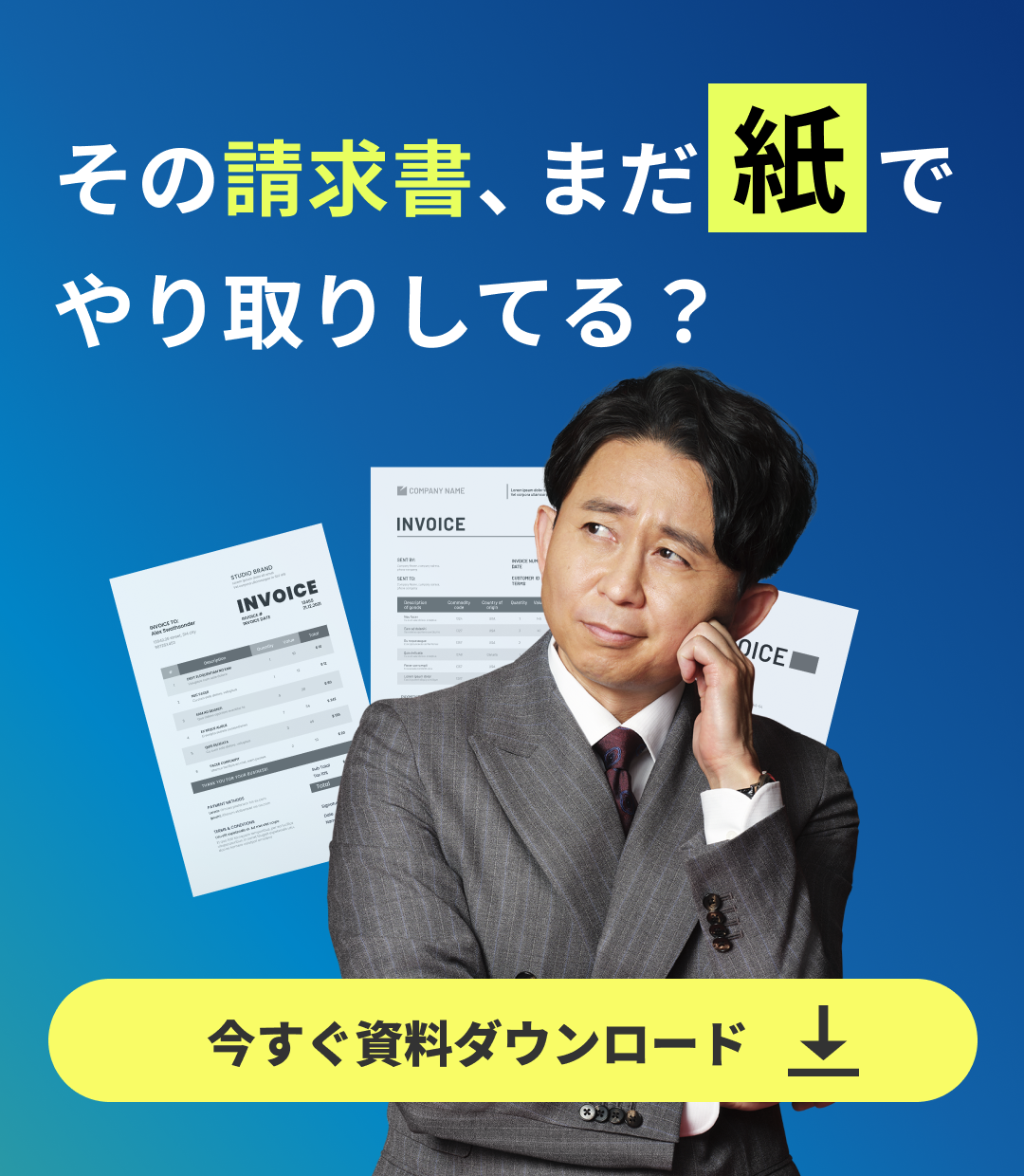インボイス制度の基礎知識

まずは、インボイス制度の概要について簡単に確認しておきましょう。
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除に関する新制度で、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。
インボイス制度が開始された2023年10月1日以降、消費税の仕入税額控除を受けるためには適格請求書(通称:インボイス)の適正保存が必要になります。
そして、適格請求書を発行することができるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者のみとなります。
そのため、インボイス制度の開始に向けて、免税事業者は「課税事業者になるか否か」、課税事業者は「免税事業者との取引を継続するか否か」の判断を迫られている状況だと言えます。
個人事業主への影響が大きい理由とは?

次は、個人事業主にとってインボイス制度の影響が大きいとされている理由を確認していきましょう。
先述の通り、インボイス制度開始後に適格請求書を発行するには適格請求書発行事業者になる必要があり、2023年10月以降、免税事業者のままでは適格請求書を発行することができません。
そして、個人事業主の多くは課税売上高が1,000万円以下の免税事業者に該当することから、課税事業者に切り替えて適格請求書発行事業者になるか否かの判断を迫られているのです。
しかし、免税事業者から課税事業者になることで、これまで免除されてきた税金の納付および納税関連の事務処理が必要になるため、個人事業主にとって大きな負担となりかねません。
一方で、免税事業者のままでいることで、取引を見直されてしまうケースや、場合によっては消費税分の値引きを要求されるケースも考えられるでしょう。
つまり、インボイス制度には免税事業者にとって不利なルールが仕掛けられており、免税事業者に対して課税事業者への転換を促す制度になっていると言えます。
このような理由から、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主はインボイス制度による影響が大きいと言われているのです。
インボイス制度対応のポイント

次は、免税事業者の個人事業主の立場、そして個人事業主との取引がある企業の立場から、それぞれインボイス制度対応のポイントを確認していきましょう。
個人事業主の対応
インボイス制度に向けた個人事業主の主な対応として、以下の4点を挙げることができます。
- 課税事業者になるか否かの判断
- 適格請求書発行事業者の登録申請
- 請求書フォーマットの変更
- 事務処理負担の軽減
それぞれ詳しく確認していきましょう。
課税事業者になるか否かの判断
まず、課税事業者になるか否かの判断が必要になります。
一般消費者が顧客のBtoC事業であれば、仕入税額控除のために適格請求書の発行を求められることもないため、免税事業者のままでも問題ない可能性があります。
ただし、一般消費者が顧客のBtoC事業者であっても、高級レストランや料亭など、会社の接待で利用されることが多い業態ならば、適格請求書発行事業者になることが求められるケースもあります。
課税事業者への売上取引があるBtoB事業の場合、基本的に取引先から適格請求書の発行を求められるため、課税事業者への切り替えが有力な選択肢となります。
ただし、すべての売上先が簡易課税制度を採用していれば適格請求書発行事業者になる必要はないため、BtoB事業であっても免税事業者のままでいられるケースも考えられます。
このように、BtoC事業、BtoB事業を問わず、事業の実態を考慮して免税事業者のままでいるか、課税事業者になるかを判断することが必要です。
適格請求書発行事業者の登録申請
課税事業者への切り替えを選択する場合、適格請求書発行事業者の登録申請を行いましょう。
通常、免税事業者が課税事業者に切り替える際には「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、インボイス制度開始に伴い課税事業者に切り替える場合は、適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録を受けたその日から課税事業者になることができます。
以下の記事では、適格請求書発行事業者の登録申請方法の手順を詳しく解説しています。あわせてお読みください。
請求書フォーマットの変更
適格請求書発行事業者の登録申請が完了したら、適格請求書の要件を満たす請求書フォーマットを準備しましょう。
適格請求書として認められるためには、以下の項目を記載する必要があります。
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごとに合計した対価の額および適用税率
(5)消費税額等(端数処理は一請求書あたり税率ごとに1回ずつ)
(6)適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
事務処理負担の軽減
免税事業者から課税事業者に切り替える場合、これまで免除されてきた納税のための事務処理を行わなければなりません。
しかし、リソースに限りがある個人事業主にとって、事務処理の負担は大きいと言えるでしょう。
そこで重要になるのが、個人事業主や中小事業者向けの特例制度の利用です。
たとえば、消費税の「簡易課税制度」を利用するのも一策です。
簡易課税制度とは、事業区分ごとに定められたみなし仕入率を用いて簡易的に納税額を算出できる制度です。
また、令和5年度税制改正により、インボイス制度開始から3年間は「2割特例」を利用可能になりました。
2割特例とは、売上税額の2割を納税額とすることができる制度で、免税事業者から適格請求書発行事業者になった事業者が利用できます。
税率ごとの売上を把握するだけで納税額の申告が可能になるため、事務処理負担を抑えることができるでしょう。
簡易課税制度や2割特例を利用することで、原則課税よりも納税額が増えてしまうケースもあり得ます。
原則課税と簡易課税、2割特例のどれが有利であるか、事前にシミュレーションするなどして判断することが大切です。
個人事業主との取引がある企業の対応
個人事業主との取引がある企業も、インボイス制度に向けて以下のような対応が必要になります。
- 免税事業者との取引について方針を決める
- 取引先の個人事業主の意向を確認
- インボイス制度開始後の運用体制整備
それぞれ詳しく確認していきましょう。
免税事業者との取引について方針を決める
インボイス制度の開始後、免税事業者からの仕入税額控除について6年間は経過措置が設けられているとは言え、控除の割合は限定的であり控除率も段階的に引き下げられます。
個人事業主などの免税事業者からの仕入れ取引が多い場合、自社で負担する消費税額が大きくなってしまいます。
そのため、インボイス制度開始後の税負担を試算するなどして、「免税事業者との取引をいつまで継続するか」という方針を決定する必要があります。
なお、自社が簡易課税制度や2割特例を選択している場合、取引先が免税事業者であっても仕入税額控除を受けることができます。
つまり、簡易課税制度や2割特例制度を選択するか否かによっても、免税事業者との取引方針は変わると言えるでしょう。
取引先の個人事業主の意向を確認
次に、個人事業主を含む免税事業者の取引先の意向を確認します。
課税事業者への切り替えおよび適格請求書発行事業者の登録申請は済んでいるか、済んでいない場合には今後行う予定があるかを確認しましょう。
取引先の回答によっては、課税事業者への切り替えを依頼したり、取引先の見直しを進めたりする必要があります。
制度開始後の運用体制整備
インボイス制度開始後、請求書受領に関わる運用フローに変更が生じます。
免税事業者と課税事業者で別々に請求書を処理する必要があるため、仕分けを行う必要があります。
また、課税事業者から受領する請求書に関しては、適格請求書の要件を満たしているか、適格請求書発行事業者の登録番号に間違いはないかなどを確認する手間が発生します。
このように、インボイス制度の開始後は今まで以上に作業が煩雑化することが予想されるため、運用体制の整備とともに請求処理の効率化に取り組むべきだと言えます。
免税事業者との取引に関する調査

ここまでは個人事業主、そして個人事業主と取引がある企業のインボイス制度対応について紹介してきました。
次は、免税事業者の取引先に対する企業の動きについて、ウイングアーク1st株式会社が実施した「インボイス制度に向けた企業間取引の電子化に関する対策調査」を基に確認していきましょう。
この調査では、免税事業者の取引先に対して課税事業者への移行を「すでに依頼した」という回答が19.8%、「依頼する予定」という回答が27.6%となっており、約半数の企業(47.4%)が依頼済み、または依頼予定であることがわかりました。
また、取引先の免税事業者が課税事業者に転換しない場合、今後の取引に「非常に影響があると思う」という回答が26.1%、「やや影響があると思う」という回答が52.6%となっており、じつに78.7%の企業が今後の取引への影響を示唆する結果となりました。
さらにこの調査では、取引先が課税事業者に変更しない場合、どれほどの期間取引を継続する意向があるかについてもアンケートを行っています。
その結果、取引先が免税事業者のままでも「1年間は取引を継続する」という回答が18.8%、「2~3年間は取引を継続する」という回答が33.8%となり、半数以上の企業が最大3年間は取引を継続する意向を示しました。
<調査概要>
- 調査名:インボイス制度に向けた企業間取引の電子化に関する対策調査
- 有効対象:100億円以上の売上の企業に所属する請求書関連業務に携わる会社員
- 有効回答数:500名(建設業101名、製造業104名、情報システム・ソフトウェア業103名、金融・保険業104名、卸売り・小売業88名)
※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。 - 調査期間:2022年12月2日〜同年12月6日
▼調査の詳細はこちら
大企業を中心としたインボイス制度対策状況を調査 インボイス制度対応中は41.0%に上昇、財務経理部門と情シス・DX推進部門間連携は3ヶ月半で約20%加速 | ウイングアーク1stコーポレートサイト
インボイス制度への対応なら「invoiceAgent」
インボイス制度が始まることで、納税に関する事務処理だけでなく、請求書関連業務の負担が増加すると予想されています。
そのため、インボイス制度への対応を進めると同時に、請求関連業務の電子化および効率化を進めることをおすすめします。
次は、インボイス制度への対応と請求関連業務の電子化を実現するソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent 電子取引(インボイスエージェント 電子取引)」をご紹介します。
請求書の送受信を電子化
「invoiceAgent 電子取引」は、請求書などの企業間取引文書の送受信を電子化することが可能です。
PDFファイルをアップロードするだけで請求書をWeb配信することができ、取引先が発行する帳票も「invoiceAgent」を介して受信することができます。
また、PDF出力する前の請求データを所定のフォルダにアップロードするだけで、自動でPDFに変換することも可能です。
これらの特徴により、紙ベースよりも効率的かつ正確に請求関連業務を行うことができるでしょう。
インボイス制度に対応する機能を搭載
「invoiceAgent 電子取引」は、デジタルインボイス(電子化された適格請求書)の標準仕様である「Peppol(ペポル)」経由のデータ送受に対応しています。
また、紙で受領した適格請求書のデータ化や、適格請求書発行事業者の登録番号確認も「invoiceAgent 電子取引」上で行うことができます。
これらの特徴により、インボイス制度に対応する運用体制をスムーズに整えることができるでしょう。
電子帳簿保存法への対応も万全
請求書などの国税関係帳簿書類を電子データとして保存する場合、電子帳簿保存法の法的要件を満たす必要があります。
「invoiceAgent 電子取引」は、電子帳簿保存法の法的要件を満たすソフトウェアに与えられる「JIIMA認証」を取得しています。
そのため、「invoiceAgent 電子取引」で帳票を送る側も受け取る側も、電子帳簿保存法に対応することが可能です。
まとめ
今回は、インボイス制度が個人事業主に与える影響や、個人事業主および取引先の企業が進めるべき対応のポイントを解説してきました。
個人事業主の方々の多くは免税事業者であり、インボイス制度による影響は非常に大きいと言えます。
免税事業者の個人事業主の方や、個人事業主との取引がある企業は、今回ご紹介した情報も参考にインボイス制度における対応を進めていきましょう。
また、インボイス制度対応とあわせて、「invoiceAgent」で請求業務の電子化・効率化に取り組んでみてはいかがでしょうか。