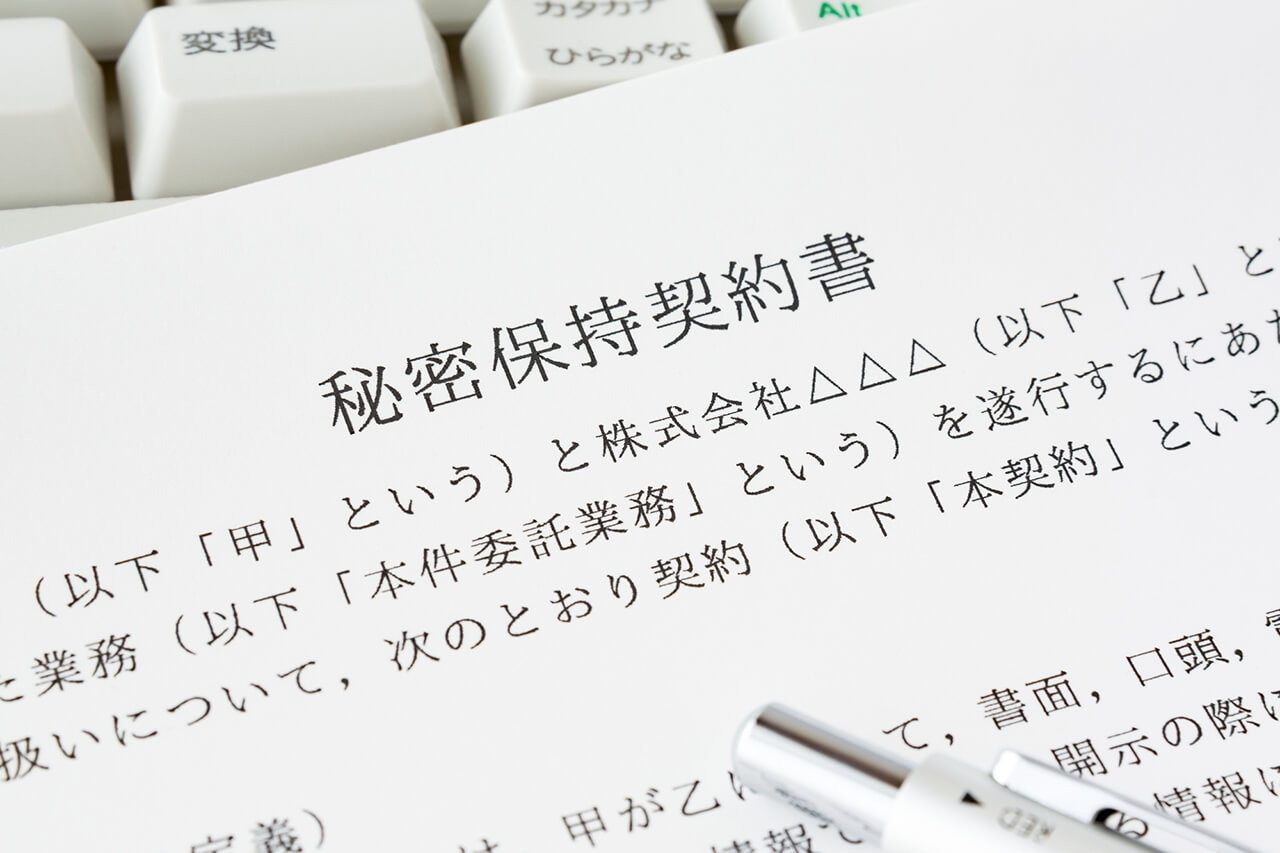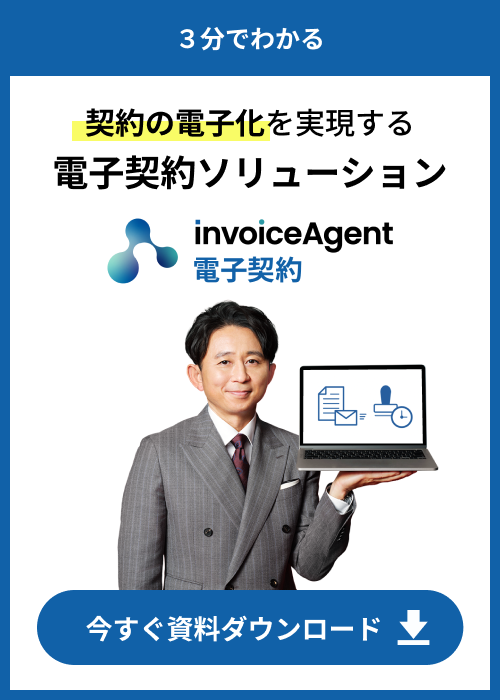秘密保持契約(NDA)の基礎知識

まずは、秘密保持契約とはどのような契約なのか、意味や必要性、締結シーンといった基礎知識を解説していきます。
秘密保持契約(NDA)とは?
秘密保持契約とは、取引などで相手方に開示・共有する情報について、本来の用途以外での使用や第三者への開示を制限するための契約です。
そして、秘密保持契約を結ぶ際に用いられるのが秘密保持契約書です。
秘密保持契約は英語で「Non-Disclosure Agreement」と表すため、頭文字を取って「NDA」とも呼ばれます。
また、「機密保持契約書」や「守秘義務契約書」と呼ぶケースもありますが、いずれも同様の意味合いだと考えて問題ありません。
秘密保持契約書の必要性
ビジネスでは、自社の経営状況や技術情報、顧客情報などを取引先や委託者に開示・共有する場面が多々あります。
こうした情報は開示側にとって機密性の高い情報であることが多く、外部に漏えいしたり不正利用されるリスクを避ける必要があります。
万が一不正利用されるなどの事態が発生した場合、金銭的損害を被る可能性があるだけでなく、企業としての信用を損なう恐れもあります。
さらに秘密保持契約は特許申請にも関わってきます。
特許法では、「公知(公然に知られた)の発明」は、特許申請することができないと定められています。
もしも機密保持契約を締結せずに共有した技術のなかに特許申請を考えている技術が含まれていた場合、「公知の発明」として特許権が認められない可能性があります。
秘密保持契約は、上記のような事態を避け、自社の秘密情報を守るために重要な役割を果たす契約だと言えるでしょう。
秘密保持契約(NDA)を締結するシーン
秘密保持契約は、相手に対して情報を開示したり共有したりする前に締結するのが一般的です。
秘密保持契約を締結するシーンとしては、たとえば以下のような場面が挙げられます。
- 他社や個人事業主に業務を委託するとき
- 従業員を雇用するとき
- 企業間で取引を開始するとき
- 企業間で資本提携や業務提携するとき
- 他社と共同で研究・開発などを行うとき
など
いずれの場合も、基本契約の締結とあわせて秘密保持契約を締結します。
基本契約を締結していて、秘密保持契約は締結していないという場合には、速やかに相手方に申し入れて、秘密保持契約を締結することを推奨します。
秘密保持契約書に収入印紙は必要?
秘密保持契約書でよくある疑問のひとつが、収入印紙の貼付が必要かどうかです。
契約書の内容や種類によっては印紙税法上の課税文書に該当し、収入印紙の貼付が必要になるためです。
秘密保持契約書の場合、基本的には収入印紙の貼付は必要ありません。
ただし、業務請負に関する内容など、課税文書に該当する内容が含まれる場合には、「秘密保持契約書」という名目であっても収入印紙の貼付が必要になる可能性があります。
秘密保持契約書の書き方
経済産業省は、「秘密情報の保護ハンドブック〜企業価値向上に向けて〜 」のなかで、目的・状況別に秘密保持契約書の雛形・参考例を公開しています。
次は、「秘密情報の保護ハンドブック〜企業価値向上に向けて〜 」で公開されている「業務提携・業務委託等の事前検討・交渉段階における秘密保持契約書の例」を参考にしつつ、秘密保持契約書の記載項目や書き方のポイントを解説していきます。
参考:秘密情報の保護ハンドブック〜企業価値向上に向けて〜 |経済産業省
- 表題(タイトル)
- 前文
- 秘密情報の定義
- 秘密情報の取扱い
- 返還義務
- 損害賠償
- 有効期限
- 管轄裁判所
- 後文
表題(タイトル)
表題(タイトル)として、「秘密保持契約書」と書面の冒頭に記載します。
また、「秘密保持契約書(〇〇の契約に関して)」のように、具体的な契約内容について記載しても問題ありません。
前文
契約の当事者と主題を明確にするため、前文を記載します。
たとえば、「〇〇の共同研究にあたって相互に開示する情報の取扱いについて、以下の通り秘密保持契約を締結する」といった具合です。
秘密情報の定義
どの情報が秘密情報に該当するのかを明確にするため、秘密情報の範囲を定義します。
秘密情報の定義が不明瞭な場合、万が一情報の不正利用や漏えいが発生した際に責任を問えない可能性があります。
「自社が開示する一切の情報」や「開示の際に秘密であることを明示した情報」といった具合に、秘密情報に該当する範囲を定めましょう。
秘密情報の取扱い
秘密情報の取扱いについて記載します。
たとえば、開示した秘密情報の管理方法や、目的外での使用禁止、複製の制限、漏えいや紛失が発生した場合の対処などです。
返還義務
秘密情報を含む記録媒体などの返還義務について規定します。
秘密情報が不要になった場合や開示者からの請求がある場合、直ちに開示者に秘密情報を含む記録媒体や複製物を返還あるいは消去するように明記します。
損害賠償
契約違反があった場合の損害賠償について記載します。
開示した情報の不正利用や漏えいなど、当該契約で規定した条項に違反した場合に、相手方に生じた損害を賠償することを明記しましょう。
有効期限
契約の有効期限について記載します。
たとえば、「契約の締結日から起算して〇年間」といった具合に、期限を明確に記しましょう。
また、「期間満了後の〇ヶ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する通知がない場合、本契約は同一条件で〇年間継続するものとする」のように、有効期限の延長・継続に関する内容もあわせて記載しましょう。
管轄裁判所
当該契約に関する訴訟に発展した場合の管轄裁判所を明記します。
たとえば、「東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする」といった形です。
後文
後文として、「契約書を何通作成したのか」、「誰が契約書を保有するのか」を明記します。
2社間の秘密保持契約であれば、「本契約の成立の証として、本契約書を2通作成し、甲乙各1通を保有するものとする」のように記載します。
秘密保持契約(NDA)締結の流れ

次に、秘密保持契約(NDA)を締結する際の基本的な流れを解説します。
一般的に、秘密保持契約の締結は以下のようなステップで進みます。
- 双方による契約内容の協議
- 秘密保持契約書のドラフト(草案)作成
- 双方によるドラフト確認・修正
- 秘密保持契約書原本の作成・締結
各ステップについて詳しく確認していきましょう。
1. 双方による契約内容の協議
秘密保持契約書を作成するにあたり、当事者双方によって契約内容の協議を行いましょう。
秘密情報の定義や範囲、情報漏えい時の措置など、秘密保持契約書に記載する内容を決定していきます。
企業間でのNDA締結の場合は、どちらが契約書を作成するのかも明確にしておきましょう。
一般的には情報を開示する側の企業が契約書を作成するのが通例となっています。
2. 秘密保持契約書のドラフト(草案)作成
協議した内容を踏まえ、秘密保持契約書のドラフト(草案)を作成します。
雛形を用意しているのであれば、それをベースにしつつ協議した契約内容を盛り込んでいきます。
雛形をそのまま利用してしまうと、実際の状況とはかけ離れた秘密保持契約書になってしまい、有効に機能しないリスクがあります。
NDA締結の目的・場面・開示情報といった個別の事情に応じて、適宜契約内容を調整することが大切です。
3. 双方によるドラフト確認・修正
秘密保持契約書のドラフトを作成したら、当事者双方で内容の確認を行います。
協議した内容は適切に記載されているか、追加で盛り込むべき条項はないかなど、抜け漏れがないか双方でしっかりと確認し、双方が内容に合意するまで適宜協議・修正を重ねます。
4. 秘密保持契約書原本の作成・締結
ドラフトの確認・修正を経て、最終的に双方の合意に至った段階で秘密保持契約書の原本を作成します。
原本を二部作成(二者間での契約の場合)し、内容を最終確認して署名捺印します。
署名捺印が完了したら相手方に原本を郵送し、相手方でも最終確認と署名捺印を行い、一部は相手方で保管、もう一部は自社で保管するために返送してもらいます。
秘密保持契約(NDA)の締結は電子化できる
秘密保持契約(NDA)を締結する流れについて解説しましたが、秘密保持契約は締結までに時間がかかりやすく、とくに書面で秘密保持契約書を運用している場合にはさらに多くの手間と時間がかかってしまいます。
秘密保持契約の締結を効率化・迅速化するには、電子契約の導入が有効です。
電子契約とは、インターネットを介して締結する契約の形式です。
電子文書に「電子署名」や「タイムスタンプ」などを付与することで、書面における署名や押印に相当する効力を持たせることができます。
そして、秘密保持契約も電子契約での締結が可能です。
ビジネスシーンでは秘密保持契約に限らずさまざまな場面で契約を締結することから、電子契約を導入することで大幅な業務効率化につなげることができるでしょう。
「invoiceAgent 電子契約」で面倒な契約作業を効率化!
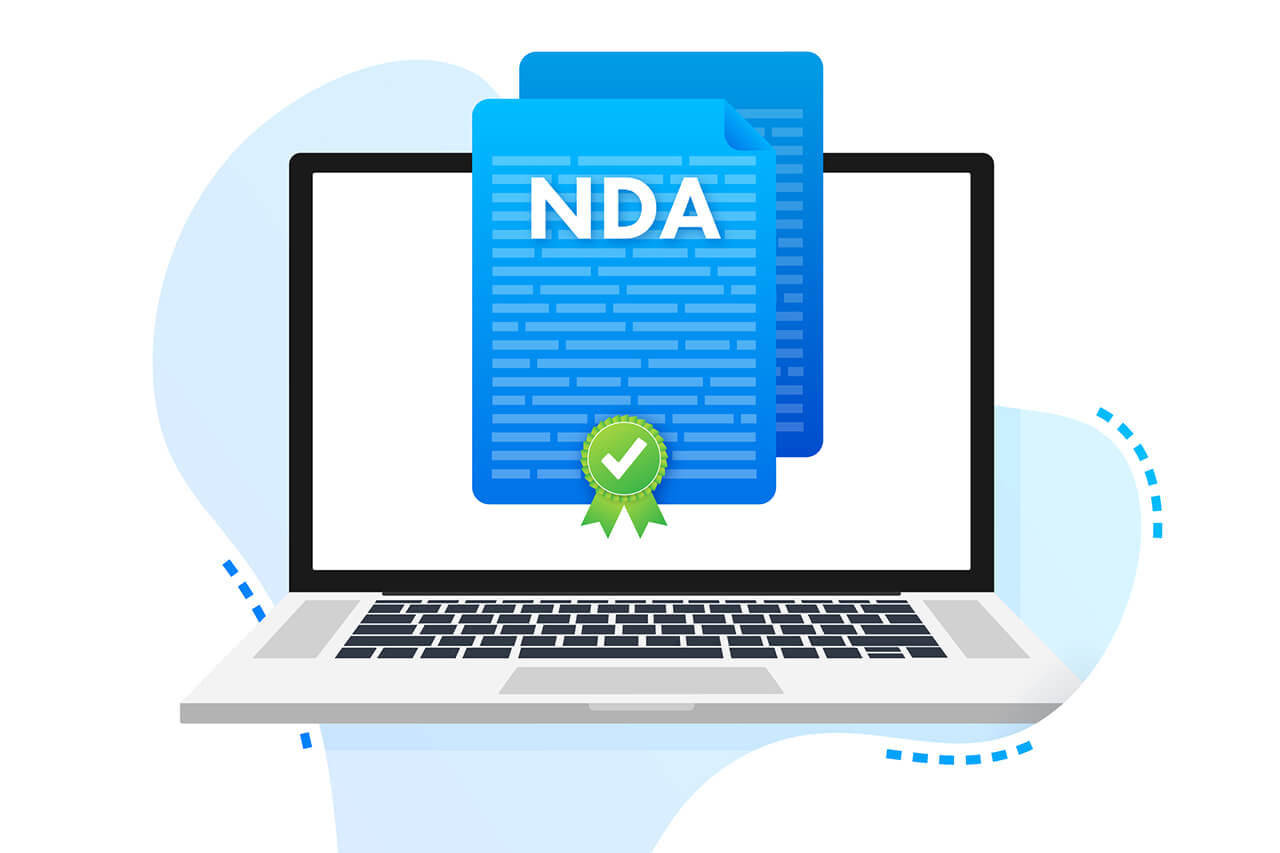
秘密保持契約(NDA)の締結を効率化するには、電子契約が有効だとお伝えしました。
そして、秘密保持契約をはじめ、ビジネスシーンで交わされるさまざまな契約に対応するソリューションが、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent 電子契約(インボイスエージェント 電子契約)」です
「invoiceAgent 電子契約」は、商取引における契約の確認・署名・管理を一気通貫で実現するクラウド型の電子契約ソリューションです。
契約書の作成と承認経路の設定をシステム上で行うことができ、書面による契約締結と同じように自社・取引先での社内承認・署名を行えます。
また、双方の社内承認・署名が完了した契約書に対し、ウイングアーク1stが立会人となってタイムスタンプと電子署名を付与することで、「電子文書の成立が真正」であることを証明して電子契約の有効性を担保します。
さらに、「invoiceAgent」のシリーズ製品と連携することで、契約書を含む各種ビジネス文書の送受信や管理を電子化したり、紙文書のデータ化を実現することも可能です。
まとめ
今回は、ビジネスシーンで締結する機会が多い秘密保持契約(NDA)について解説しました。
自社の秘密情報を守り、無用なトラブルを回避する上で、秘密保持契約書は非常に重要な役割を果たします。
そして、秘密保持契約をはじめ、ビジネスにおける各種契約手続きを効率化するには、電子契約の導入が有効です。
現在、秘密保持契約書などの契約書を書面で作成・管理している方は、今回ご紹介した情報も参考に「invoiceAgent 電子契約」で契約業務を効率化してみてはいかがでしょうか。