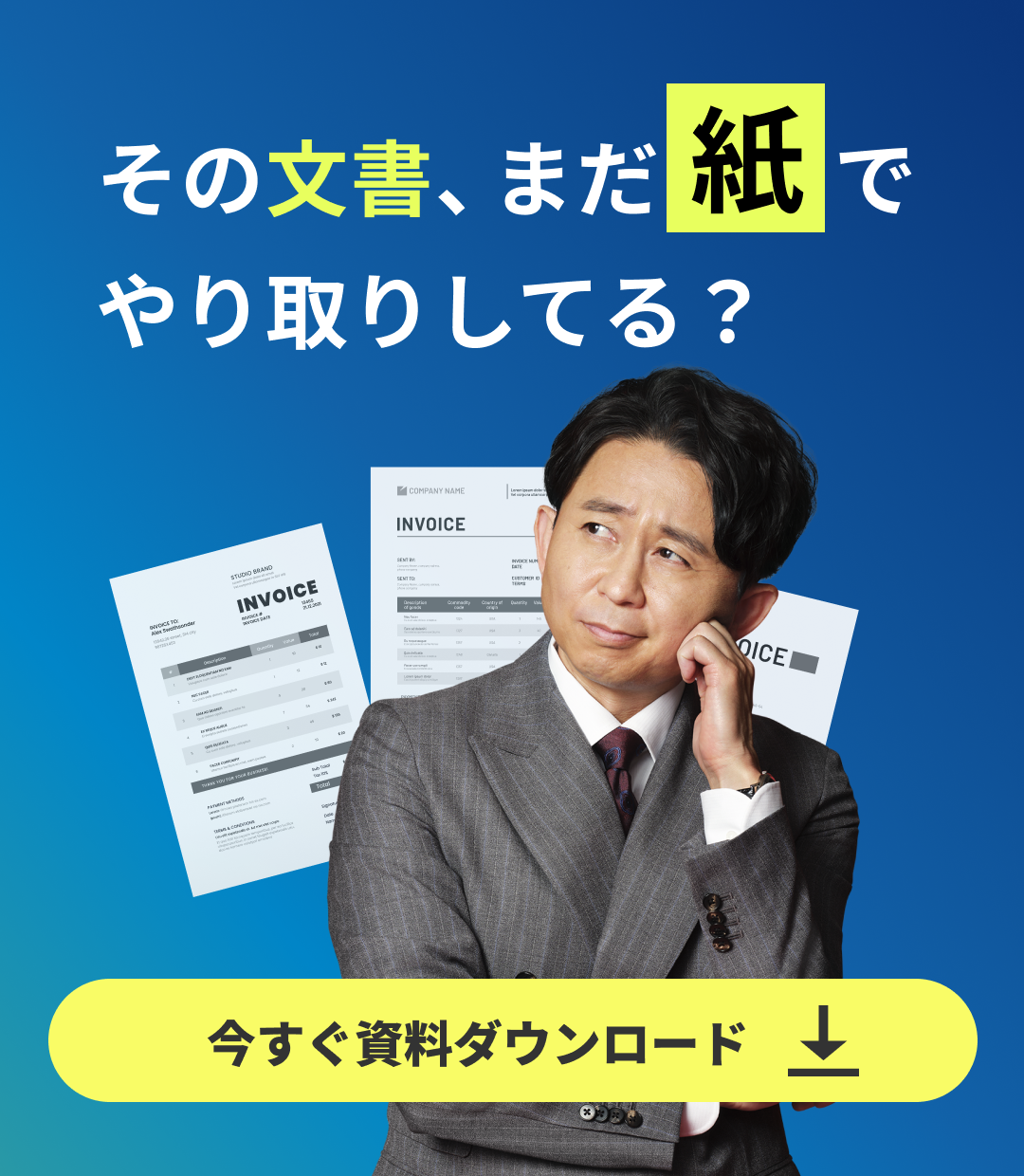業務改善の基礎知識
まずは業務改善の基礎知識として、その意味や混同しがちなBPR(業務改革)との違いについて確認していきましょう。
業務改善とは?
業務改善とは、既存の業務の見直し・改善を継続的に行い、生産性向上や市場競争力の強化を図るプロセスを指します。
企業は、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源を活用し、顧客にとって価値のある商品・サービスを提供することで利益を得ます。
しかし、業務のなかに「ムリ・ムダ・ムラ」が存在すると、経営資源を最大限に活用することができず、「品質の低下」や「費用の増加」、「納期の遅延」を招き、結果として生産性や市場競争力の低下につながる恐れがあります。
こうした事態を回避し、労働生産性や市場競争力を高めていくために、業務改善の取り組みが必要となるのです。
業務改善とBPR(業務改革)の違い
業務改善としばしば混同されるキーワードに「BPR」があります。
BPRは「Business Process Re-engineering(業務改革)」の頭文字をとったもので、業務全体を抜本的に見直して再構築するプロセスを指します。
業務改善は「既存の業務の流れを保ちつつ改善を図る」のに対し、BPRは「業務全体をゼロから再構築する」という点が大きな違いと言えるでしょう。
業務改善に取り組むべき理由
国内企業における業務改善の重要性が高まっている理由として、大きく以下の2点を挙げることができます。
- 少子高齢化による労働力不足
- 日本の労働生産性の低迷
次は、業務改善に取り組むべき理由について詳しく確認していきましょう。
少子高齢化による労働力不足
業務改善が必要とされる理由として、労働力不足を挙げることができます。
少子高齢化が進む日本では、生産年齢人口が年々減少しており、この傾向は今後も長期にわたって続くと言われています。
すでにさまざまな業界で労働力不足が深刻な課題となっており、限られた人員で事業を継続していく工夫が必要となっています。
一方、政府が主導する働き方改革によって、長時間労働の是正をはじめとした労働環境の改善も同時に求められています。
労働時間を維持・削減しつつ、限られた人員で事業を継続していくためには、既存の業務を見直し改善していく取り組みが不可欠と言えるでしょう。
日本の労働生産性の低迷
業務改善の重要性が高まっている理由として、日本企業の労働生産性の低迷も挙げることができます。
公益社団法人日本生産性本部が公開している「労働生産性の国際比較2021」によれば、2020年の日本の時間当たり労働生産性はOECDに加盟する38ヶ国中23位、一人当たり労働生産性は28位となっており、いずれもデータを取得できる1970年以降でもっとも低い順位となっています。
IT技術の発展によりグローバル化が進む現代、日本企業が競争力を高めてグローバル市場で勝ち残るためには、業務改善に取り組み生産性を高めていくことが重要だと言えるでしょう。
(参照:労働生産性の国際比較 | 調査研究・提言活動 | 公益財団法人日本生産性本部)
業務改善の基本的な取り組み方
次に、業務改善の基本的な進め方について確認していきましょう。
業務改善は大きく以下4つのステップで構成されており、PDCAを回して継続的に取り組むことが大切です。
- 業務の可視化(見える化)
- 課題の特定・整理
- 計画の策定・実行
- 評価と改善
では、業務改善の各ステップについて見ていきましょう。
1.業務の可視化(見える化)
業務改善の最初のステップは、業務の可視化(見える化)です。
一連の業務フローのなかで、「誰が」「何を」「どのように」行っているのかが明確でない場合、改善するべき課題の発見や計画の策定・実行、効果の検証を適切に行うことができません。
業務改善のPDCAを回すための土台となるステップですので、現場担当者にヒアリングを行いつつ、業務の工程や内容を可視化していきましょう。
2.課題の特定・整理
ステップ1で可視化した情報をもとに、現状の課題を特定していきます。
業務の一連の流れのなかで、「ムリ・ムダ・ムラ」が発生している、もしくは発生しうる工程がないかを確認しましょう。
次に、洗い出した課題の優先度を整理していきます。その際、業務全体への影響の大きさと、改善する場合の取り組みやすさを考慮して、優先順位を決定しましょう。
3.計画の策定・実行
優先的に対応する課題について、具体的な実行計画を策定します。
課題を解消するために考えうる対策を洗い出して、実現可能性や必要工数・コストも考慮しつつ実施する対策を決定しましょう。
また、対策を実施するにあたって具体的な改善目標を設定し、目標達成に向けたタスクとスケジュールを整理します。
計画の策定が完了したら、関係者に計画の内容と目標を周知したうえで実行していきます。
4.評価と改善
業務改善の取り組みは、計画を一度実行して終わりではなく、中長期的な視点を持って継続していくことが大切です。
実行した計画によって、想定した目標を達成できたのか、達成・未達成の要因は何だったのか、といった点を評価・検証します。
評価・検証の結果と得られた知見を活かし、さらなる業務改善に取り組んでいきましょう。
業務改善に役立つアイデア・ツール
次に、業務改善に役立つアイデアとして以下の5つをご紹介します。
- 文書の電子化・ペーパーレス化
- ノンコア業務の詔勅化・自動化
- コミュニケーション方法の見直し
- データ活用・分析の推進
- 人材配置の最適化
各アイデアについて、有効なツールとあわせて確認していきましょう。
文書の電子化・ペーパーレス化
業務改善に効果的な取り組みのひとつが、文書の電子化・ペーパーレス化です。
企業では、請求書や契約書といった社外向けの文書や、稟議書や申請書といった社内文書など、日々さまざまな文書が扱われています。
これらの文書を紙ベースで運用している場合、書面の印刷や、手作業による回覧や押印、目視による入力・照合作業など、非効率・非生産的な作業が多く発生してしまいます。
文書の電子化・ペーパーレス化を推進することで、上記のような作業を省略したり効率化することが可能です。
文書の電子化に役立つツールとして、電子帳票システムや電子契約システム、ワークフローシステムなどを挙げることができます。
また、文書の電子化・ペーパーレス化は、後述する「ノンコア業務の省力化・自動化」や、「データ活用・分析の推進」の土台にもなるため、業務改善の第一歩として非常に有効だと言えるでしょう。
ノンコア業務の省力化・自動化
ノンコア業務の省力化・自動化もまた、業務改善に有効な取り組みです。
ノンコア業務とは、直接的に利益を生み出さない業務を指し、書類作成やデータ入力といった定型作業が代表的です。
RPAツールなどを利用してノンコア業務を省力化・自動化することで、より付加価値が高い業務に注力することができ、生産性向上につなげることができるでしょう。
また、先述した文書の電子化・ペーパーレス化が進んでいれば、RPAツールの利用範囲を広げることができ、より多くのメリットを享受することができるでしょう。
コミュニケーション方法の見直し
コミュニケーション方法の見直しも、業務改善に有効なアイデアです。
たとえば、文書を回覧して共有事項を伝達している場合、チャットツールや社内SNSなどを使うことで情報伝達をスピードアップできる可能性があります。
また、従来対面で行っていた会議や商談などを、オンライン会議システムを利用してWebで行うことで、移動にかかる時間やコストを削減することができるでしょう。
データ活用・分析の推進
効率的に業務改善を進めるには、客観的なデータに基いてPDCAを回すことが大切です。
そのためにも、データ活用・分析基盤の構築は非常に重要だと言えるでしょう。
たとえば、BIツールを導入することで、社内に蓄積されたデータやIoT機器から収集したリアルタイムデータを可視化することが可能です。
また、先述した文書の電子化・ペーパーレス化によって文書内の情報がデータ化されていれば、データ活用の幅が広がり、より精度の高い分析を行うことができるでしょう。
人材配置の最適化
業務の方法を変更する以外に、人材配置を見直すことで業務改善を図ることも可能です。
適材適所の人材配置を行うことで、従業員が本来持つスキルや特性を最大限に活用することができるかもしれません。
たとえば、タレントマネジメントシステムを利用して従業員に関する情報を一元管理することで、適切な人材配置や評価・育成につなげることができます。
業務改善の第一歩に「invoiceAgent」
先述した業務改善に役立つアイデアの項で、業務改善の第一歩として文書の電子化・ペーパーレス化が有効だとお伝えしました。
次は、文書の電子化および業務改善に役立つ具体的なソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent(インボイスエージェント)」をご紹介します。
企業間取引の電子化なら「invoiceAgent 電子取引」
「invoiceAgent 電子取引」は、請求書をはじめとした企業間取引文書の電子配信を実現するソリューションです。
既存のフォーマットを変更することなく、PDF化した帳票データをアップロードするだけで双方向の電子配信が可能になります。
複数の取引先とのやり取りを「invoiceAgent 電子取引」上で完結することができるため、取引の効率化や迅速化に効果的です。
また、帳票を送る側・受け取る側のどちらも電子帳簿保存法に対応することができ、2023年10月に始まるインボイス制度に対応する機能も搭載予定となっています。
契約業務の電子化なら「invoiceAgent 電子契約」
「invoiceAgent 電子契約」は、契約業務の電子化・効率化を実現するソリューションです。
契約書の作成から社内確認、双方の署名による締結、契約書の管理まで、契約に関わる一連の作業をクラウド上で完結することが可能です。
また、契約締結に際してウイングアーク1stが電子署名とタイムスタンプを付与し、完了証明書を発行します。
これらの特徴により、法的な効力を担保しつつ契約業務の電子化・効率化を実現することができます。
文書管理の電子化なら「invoiceAgent 文書管理」
「invoiceAgent 文書管理」は、文書管理の電子化を実現するソリューションです。
「invoiceAgent」はもちろん、他システムで作成・出力した文書データもまとめて取り込み、あらかじめ設定したルールに基づき自動で保存するため、手動と目視による仕分け作業を削減することができます。
また、保存した文書データは、高度な検索機能によって速やかに参照・出力することが可能です。
さらに、証跡管理機能や保存期間に応じた自動削除機能により、文書のライフサイクルを適切かつ効率的に管理することが可能です。
紙文書のデータ化なら「invoiceAgent AI OCR」
「invoiceAgent AI OCR」は、紙文書のデータ化を実現するソリューションです。
高精度な5つのOCR(光学的文字認識)エンジンと、読み取り画像の自動補正機能によって、活字・手書きを問わず高い精度で文書をデータ化することができます。
そのため、目視による確認作業や手動による入力作業といったノンコア業務を効率化・自動化することが可能です。
また、紙文書の情報をデータ化することで、これまでに蓄積してきた情報・知見を速やかに参照・共有できるようになるほか、データ分析への活用も可能になるでしょう。
「invoiceAgent」で業務改善を推進した企業事例

最後に、「invoiceAgent」で業務改善を推進した企業事例をご紹介します。
航空機の内装品などの製造を手掛ける株式会社ジャムコは、「invoiceAgent」を活用して社内のワークフローデータを可視化する「案件照会システム」を構築しました。
同社には、部署単位で業務改善・効率化の取り組みを報告する「Jリード」というプロジェクトが存在し、その一環として2020年度より社内業務のDX推進プロジェクトが発足しました。
そして、この社内DX推進プロジェクトの基盤となるのが、ワークフローシステムの改善・案件照会システムの構築でした。
同社では、ワークフローシステムを活用して日々の業務内容を蓄積していたものの、自身が携わった最近のデータしか閲覧することができず、過去の案件を参照する際は情報システム担当者が個別に照会しなければなりませんでした。
そのため情報システム担当者の業務負担が大きく、知見の共有が制限されている状況も課題となっていました。
こうした課題の解消に向け、ワークフローシステムと「invoiceAgent」を組み合わせた案件照会システムを構築。
ワークフローデータをPDF化して「invoiceAgent」に格納する仕組みによって、社員が各自で案件データを検索できるようになり、情報システム部門で行っていた案件照会業務を削減することに成功しました。
さらに、同社では業務改善提案を全社員が年1回以上行うルールがあり、そうした提案書も検索できるようになったことで、知見共有の活性化に効果を得ています。
▼事例詳細はこちら
株式会社ジャムコのinvoiceAgent導入事例をもっと見る
まとめ
今回は、業務改善の意味や必要性、取り組み方やアイデアをご紹介しました。
業務改善は、中長期的な視点を持って継続的に取り組むことが大切です。
そして、本記事で紹介したアイデアのなかでも、文書の電子化・ペーパーレス化は業務改善の推進に非常に効果的です。
今回ご紹介した情報も参考に、「invoiceAgent」で業務改善の第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。