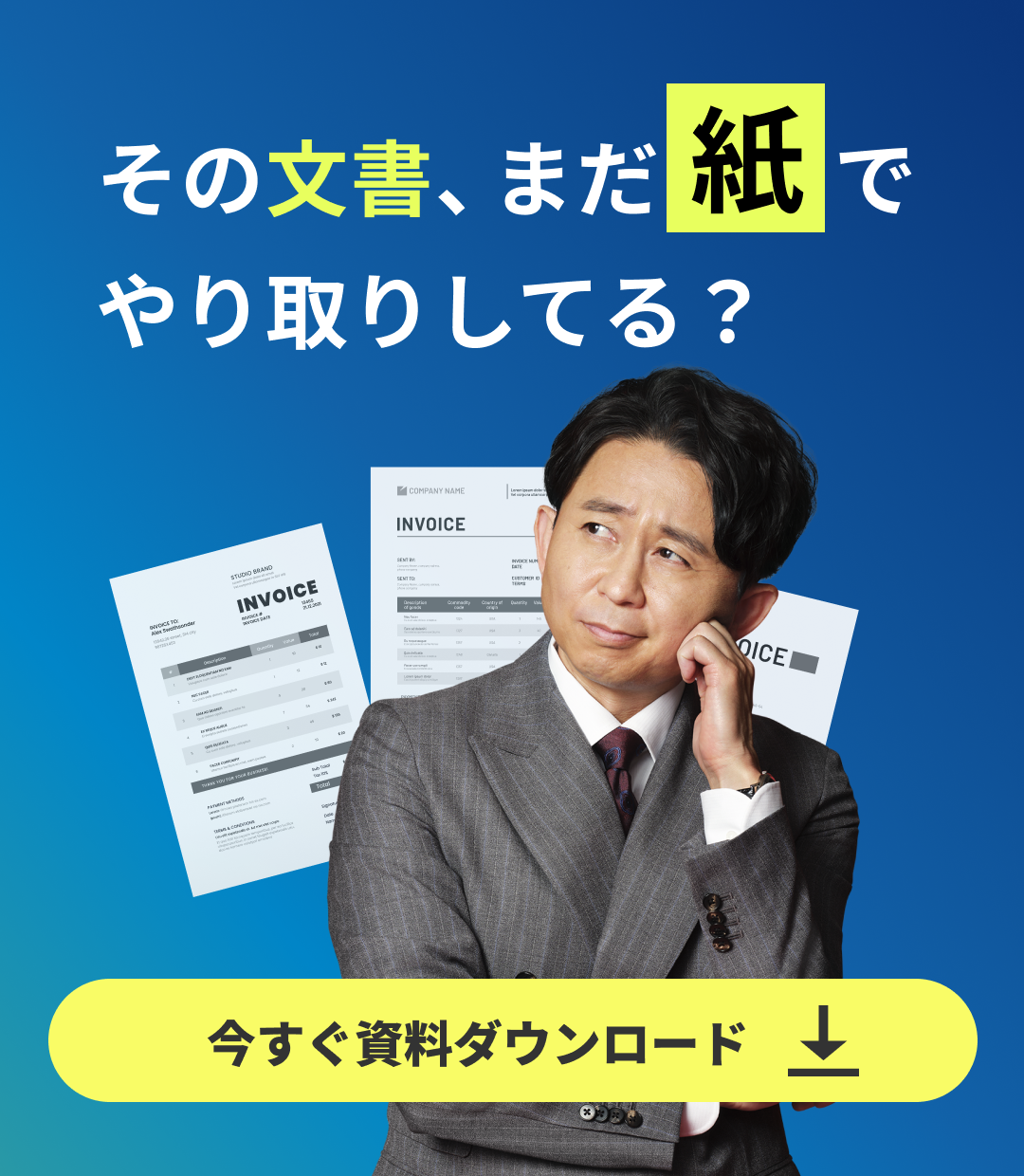書類を添付するメール本文の書き方は?

まずは、メールで書類を送付する場合の本文の書き方について、例文も交えて紹介していきます。
メールの書き方のポイント
メールで書類を送付する際、以下のポイントを踏まえて本文を書くことが大切です。
- 何を添付しているのかを明確に伝える
- 質問等の問い合わせ先を明記する
では、各ポイントについて詳しく確認していきましょう。
「何を添付しているのか」を明確に伝える
メールに書類を添付する際は、件名や本文で「何を添付しているのか」を明確に伝えることが大切です。
記事後半でも触れますが、サイバー攻撃の手法に添付ファイルを用いた「標的型攻撃メール」があり、メールを受信した相手は安易に添付ファイルを開くことができません。
また、件名や本文内で添付ファイルの存在について伝えなければ、受信者が添付ファイルに気づかない可能性もあります。
受信者に確実かつ安心して書類を受け取ってもらうためにも、「ファイルを添付していること」と「添付ファイルの内容」を明記しましょう。
質問等の問い合わせ先を明記する
添付ファイルの内容に関する問い合わせ先をメール本文に記載しましょう。
添付する書類の内容によっては、送信者以外が問い合わせ窓口となるケースもあるでしょう。
受信者側で内容について不明点や間違いがあった場合、早急に対応しなければならないケースもあるため、問い合わせ先を明記しておくことが大切です。
たとえば、メールの送信者が担当者である場合は、
と記載しておけばよいでしょう。
送信者とは別に担当者がいる場合は、
〇〇株式会社〇〇部 〇〇 〇〇
TEL:03-1234-5678
E-mail:〇〇@〇〇.co.jp
のように記載しておけば問い合わせ先がわかりやすいでしょう。
書類を添付したビジネスメールの例文
紹介したポイントを踏まえて、書類を添付したメールの例文を見てみましょう。
本文:
株式会社△△
△△ △△様
お世話になります。
〇〇株式会社〇〇部〇〇です。
お問い合わせいただきました〇〇に関する資料を、添付ファイル(.pdf形式)にてお送りします。
ご査収のほどよろしくお願い申し上げます。
添付ファイル:〇〇に関する資料_202302.pdf
添付ファイルに関してご不明点がございましたら、下記担当までお問い合わせください。
何卒よろしくお願いいたします。
=========================
〒123-4567
東京都〇〇区1-2-3 〇〇ビル1F
TEL:03-1234-5678
E-mail:〇〇@〇〇.co.jp
〇〇株式会社〇〇部
〇〇 〇〇
=========================
上記はあくまで一例ですので、送信先との関係性や添付ファイルの内容に応じてアレンジしてみましょう。
メールに書類を添付する際のマナーや注意点とは?

ここまではメールで書類を送付する際の本文の書き方を紹介してきましたが、添付するファイルに関するマナーや注意点を紹介します。
わかりやすいファイル名を付ける
添付ファイルの内容を本文で明確に伝えることが大切とお伝えしましたが、添付ファイル自体のファイル名にも配慮が必要です。
重要なポイントは、以下の2点です。
- 内容が端的に伝わるファイル名を付ける
- 「日付」や「バージョン」をファイル名に含める
まず、何に関するファイルかを明確にするため、「請求書」や「見積書」、あるいは「〇〇に関する資料」など、添付する書類の名称をファイル名に含めます。
ただし、上記だけでは他のファイルと名前が重複してしまう可能性が高いと言えます。
「請求書_20230123」や「〇〇に関する資料_ver1.0.1」のように、書類の名称の後に日付やバージョンを記載して、区別しやすく管理しやすいファイル名を付けましょう。
添付ファイルの形式・サイズに注意
メールで書類を送付する場合は、添付ファイルの形式(フォーマット)に注意しましょう。
書類であれば、PDFファイルに変換・出力して添付するのが一般的です。
ExcelやWordなどで作成した書類をそのままの形式で送信すると、文書内の情報を容易に書き換えることができてしまいます。一方、PDFファイルは修正や改ざんが難しいため、書類の原本性を担保することができます。
また、添付するファイルのサイズ(容量)にも注意が必要です。
メールサービスによって異なりますが、添付できるファイルサイズには上限があり、上限を超えた場合には正常に送信することができません。
また、上限に達していない場合であっても、容量が大きいファイルは受信側のメールボックスの容量を圧迫してしまうため、大容量のファイルを添付するのは避けるべきだと言えます。
一般的に、メールにファイルを添付する際はファイル容量を2MB以内に収めるべきとされています。送りたいファイルのサイズが大きい場合には、後述するクラウドサービスによるファイル共有も検討してみましょう。
電帳法対応が必要になるケースも
添付する文書の種類によっては、電子帳簿保存法(通称:電帳法)への対応が必要になります。
電帳法は、紙媒体での保存が原則とされている国税関係帳簿書類について、一定要件を満たした場合に限り電子保存を認める法律です。
たとえば、請求書や見積書などをメールで授受する行為は、電帳法の「電子取引」に該当するため、送信者・受信者のどちらも電子取引要件を満たす運用体制が求められます。
以下の記事では電帳法の電子取引について詳しく解説しているので、気になる方はあわせてお読みください。
セキュリティリスクを把握する
メールにファイルを添付して送る方法は、セキュリティリスクの観点から敬遠される可能性があります。
これは、メールを送る経路で悪意を持った第三者に傍受されてしまうリスクがあるほか、先述の通り添付ファイルを用いたサイバー攻撃が脅威をふるっていることが関係しています。
とくに近年は、パスワード付きのzipファイルを添付して送信し、パスワードを別途メールで伝える方法、いわゆる「PPAP」を廃止する流れが加速しています。
安全に書類を送受信したいと考えるのならば、後述するクラウドサービスの利用も視野に入れることをおすすめします。
クラウドサービスの利用も要検討!

ここまでメールに書類を添付して送る方法について解説してきましたが、書類などのファイルを共有する方法はメールだけではありません。
メールでファイル共有する場合、ファイルのサイズによってはメールに添付できない場合があるほか、セキュリティ面にも不安が残ります。
また、添付する書類が電子帳簿保存法の対象であれば、電子取引要件に対応する運用体制を整備する必要があります。
このようなメールでのファイル共有の課題を解消するため、クラウドサービスによるファイル共有に切り替える企業が増えつつあります。
クラウド型のファイル共有サービスであれば、大容量ファイルでもストレスなく共有することができるほか、セキュリティ強度も柔軟にコントロールすることが可能です。また、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトウェアに与えられる「JIIMA認証」を取得しているサービスも存在します。
書類の送受信・管理なら「invoiceAgent」
次は、書類の共有・送受信を電子化する具体的なソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent(インボイスエージェント)」を紹介します。
「invoiceAgent」は「JIIMA認証」を取得しているため、電子帳簿保存法の要件を満たしつつ書類の共有・送受信を電子化することが可能です。
では、「invoiceAgent」の特徴を見ていきましょう。
企業間取引文書の送受信なら「invoiceAgent 電子取引」
「invoiceAgent 電子取引」は、請求書や領収書などの取引文書の送受信を電子化するソリューションです。
PDFファイルをアップロードするだけで書類を送受信することができ、複数の取引先とのやり取りを「invoiceAgent」上で完結可能です。
また、PDF化する前の帳票データのCSVファイルを所定のフォルダにアップロードしてPDFファイルを生成することも可能です。
さらに、電子帳簿保存法の電子取引要件に対応しているだけでなく、2023年10月から開始するインボイス制度に対応する機能も搭載予定です。
書類の共有・管理なら「invoiceAgent 文書管理」
「invoiceAgent 文書管理」は、文書データの一元管理を実現するソリューションです。
「invoiceAgent」や他システムで出力した文書をまとめて取り込み、指定したルールに基づき仕分け・保存を実行します。
保存した文書は、高度な検索機能で速やかに参照することができ、閲覧権限を個別に設定することも可能なので、社内での書類共有の効率化につなげることができます。
また、文書の保存期間に応じた自動削除機能や改ざんの防止・検知に役立つ証跡管理機能を備えているので、効率的な文書管理を実現可能です。
「invoiceAgent」で書類のWeb配信を実現した事例
最後に、「invoiceAgent」を使って書類のWeb配信を実現した事例をご紹介します。
請求書のWeb配信により作業時間が3分の1に短縮(アスノシステム)

「会議室.COM」などのサイト運営事業を手掛けるアスノシステム株式会社は、「invoiceAgent」で請求書のWeb配信化に成功しています。
同社では以前、Salesforceから発行された請求書などの帳票を郵送で取引先に送付する運用を行っていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の流行拡大により取引先のリモートワークが進んだことで、請求書をメール添付で送付するケースが増加。
従来の郵送作業にメール添付による配信が加わったことで、事務作業が煩雑化してしまいました。
そこで同社は、「invoiceAgent」を導入して請求書をWeb配信する仕組みを構築。
導入後、負担になっていたメール添付による送付が“ゼロ”になり、請求書発行にかかっていた作業時間を3分の1に短縮することに成功しています。
▼事例詳細はこちら
アスノシステム株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る
作業時間が半減し、在宅勤務も可能に(エムオーテックス)

「LanScopeシリーズ」をはじめとしたソフトウェア開発・販売を行っているエムオーテックス株式会社は、「invoiceAgent」の導入により請求書発行業務をWeb配信へと切り替えました。
同社では従来、請求書発行業務を紙ベースで行っていましたが、コロナ禍に突入したことで郵送に加えてメールでの請求書送付も行うことに。
しかし、メール本文や送付先、添付ファイルのダブルチェックは負担が大きく、紙ベースでの運用以上に工数がかかってしまいました。
この課題を解消するため、同社は「invoiceAgent」を導入して請求書発行業務をWeb配信へと切り替えました。
「invoiceAgent」の導入により、請求書発行業務の負担は大幅に軽減され、従来40時間かかっていた工数を半分まで短縮することに成功しました。
▼事例詳細はこちら
エムオーテックス株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る
まとめ
今回は、メールで書類を送付する場合の本文の書き方やマナー・注意点について解説してきました。
近年は、メールに代わるファイル共有の手段として、クラウドサービスを利用する企業が増えつつあります。
現在、メールで書類を送付している企業は、今回ご紹介した情報も参考に「invoiceAgent」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。