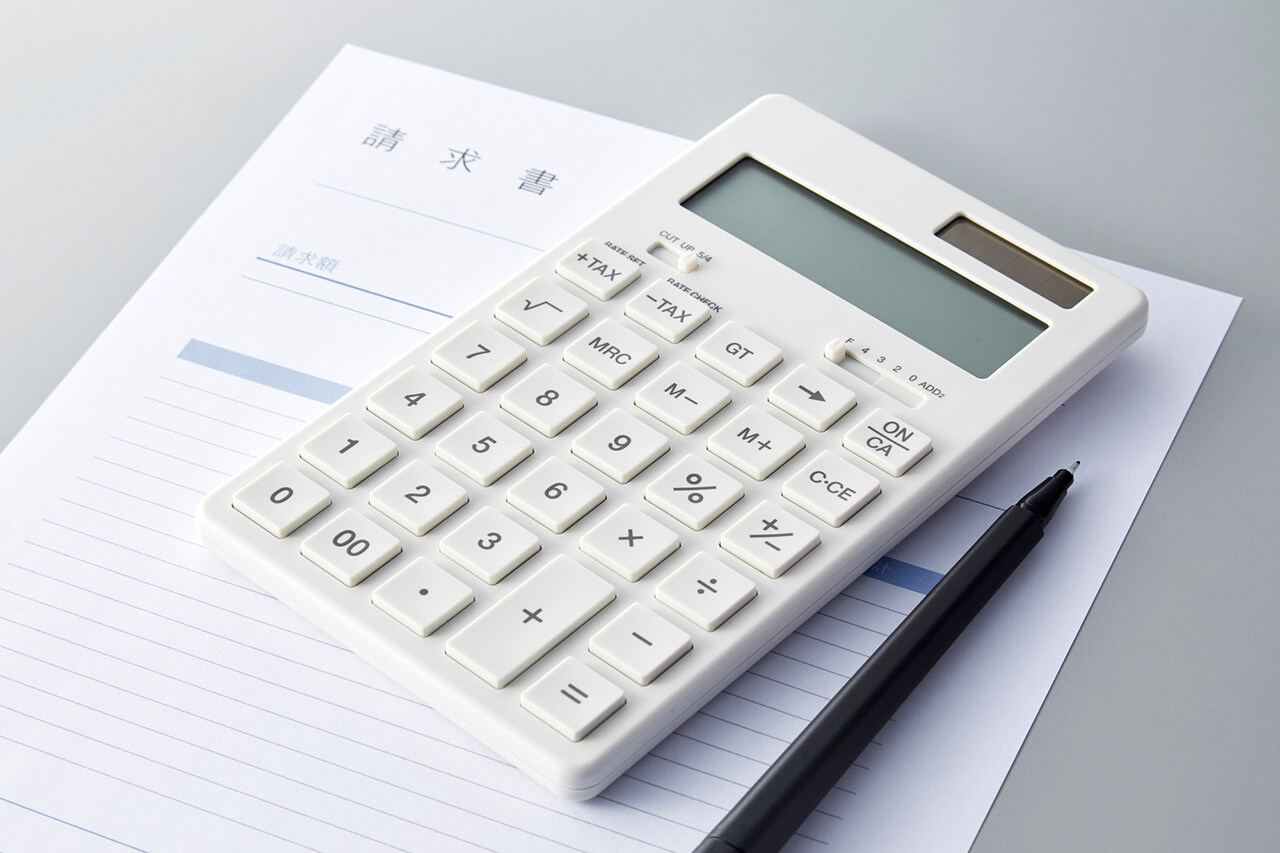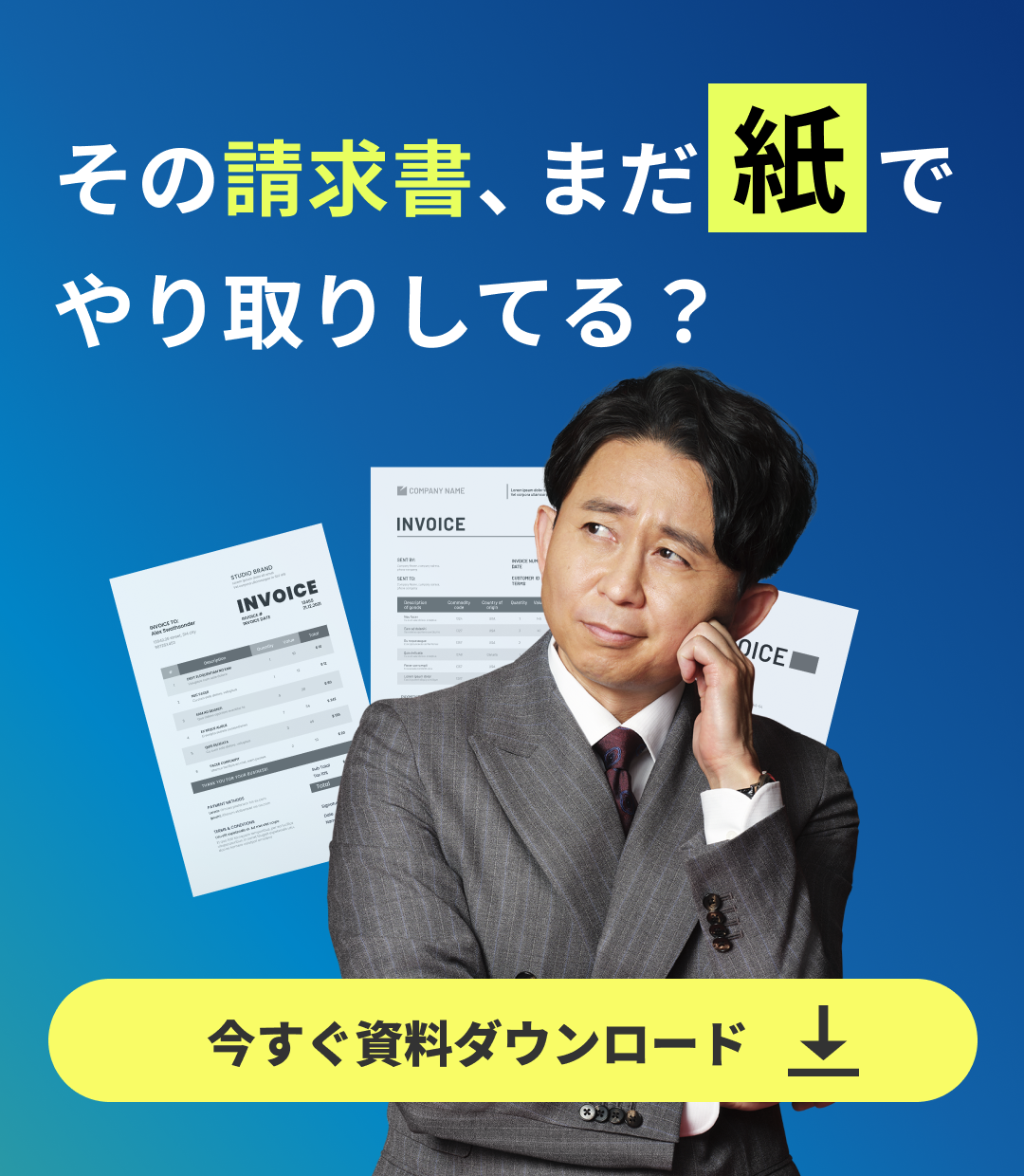請求書の端数処理の方法

請求書を作成する際、消費税の計算によって金額に1円未満の端数が生じることがあります。
請求書の金額に1円未満の端数が出た場合、処理方法として以下の3つが考えられます。
- 切り上げ
- 切り捨て
- 四捨五入
そして上記3つのうち、どの方法で端数処理を行うかは事業者の判断に委ねられています。
財務省では、消費税の端数処理に関して以下のように述べています。
「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合がありますが、その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。
(引用元:総額表示に関する主な質問 : 財務省)
ただし、採用する端数処理の方法によって請求金額に差が生じる点に注意が必要です。
たとえば、商品・サービスの税抜金額が1,999円で消費税が10%の場合、厳密な消費税額は199.9円ですが、処理方法によって以下のように違いが生まれてしまいます。
- 切り上げの場合:1円未満(0.9円)を切り上げて200円
- 切り捨ての場合:1円未満(0.9円)を切り捨てて199円
- 四捨五入の場合:1円未満(0.9円)を四捨五入して200円
たった1円と言えども、取引件数が多ければ大きな差となる可能性があるため、どの端数処理方法を採用するかしっかりと検討することが大切です。
なお、一般的には端数を切り捨てて処理している企業が多いと言われています。
請求書の端数処理に関する注意点

請求書の端数処理を行う際には、いくつか注意すべきポイントも存在します。
次は、請求書の端数処理に関する注意点を確認していきましょう。
端数処理の回数
2023年9月末までの「区分記載請求書等保存方式」においては、消費税の端数処理の回数についてルールが定められていません。
そのため、ひとつの請求書のなかで、品目ごとに端数処理を行っても、税率ごとに端数処理を行っても問題ありません。
ただし、2023年10月から開始された適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)では、端数処理の回数についてルールが定められているため注意が必要です。
端数処理方法は社内で統一する
消費税の端数処理方法は事業者に委ねられているとお伝えしましたが、社内でルールを統一することが大切です。
端数処理の方法が社内で統一されていないと、同じ商品・サービスであっても担当者によって消費税額に差が出てしまいます。
取引先との無用なトラブルを避けるためにも、端数処理に関する統一したルールを策定し、周知・徹底しましょう。
端数処理方法について取引先に事前確認
端数処理の方法について、取引先と認識を合わせておくことも大切です。
取引先との間で端数処理の方法について認識の齟齬があった場合、いざ請求する際に金額のズレが生じてしまい、トラブルにつながってしまう恐れがあります。
端数の処理方法について事前に取引先に確認し、契約書に記載しておくことで認識の齟齬を防止することができます。
納付税額の端数処理は「100円未満切り捨て」なので注意
請求書作成時などの消費税の端数処理に関しては事業者側で方法を選択することができますが、消費税の納付税額の端数処理に関しては方法が定められています。
消費税の納税額を計算する際は「100円未満切り捨て」となるため、間違えないよう注意しましょう。
インボイス制度開始後の端数処理は?

先にも少し触れましたが、2023年10月のインボイス制度開始に伴い、請求書の端数処理に関してルールや消費税の計算方法に変更があります。
次は、インボイス制度開始後の消費税の端数処理や計算方法の変更点について確認していきましょう。
税率ごとに1回ずつ端数処理を行なう
インボイス制度の開始後、仕入税額控除を受けるには適格請求書の保存が必要になります。
そして、適格請求書では「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が必要であり、「ひとつの適格請求書のなかで、税率ごとに1回ずつ端数処理を行う」というルールが定められています。
これまで品目ごとに消費税の端数処理を行っていた場合には変更が必要ですので注意しましょう。
なお、切り上げ・切り捨て・四捨五入といった端数処理の方法については、今までと同様に事業者が選択することができます。
積み上げ計算と割り戻し計算から消費税の計算方法を選択
インボイス制度がはじまると、消費税の計算方法も変わります。
現行の制度の消費税の計算は、1年間の売上総額に対して消費税を計算する「割戻し方式」のみでした。
インボイス制度の導入後は、従来の「割戻し方式」に加え、売上のたびに消費税を計算する「積み上げ方式」を選択することが可能になります。
小売店や個人向けのサービスを提供する企業など、一般消費者向けに商品・サービスを販売する業種では「積み上げ方式」の方が消費税額を抑えられるケースが多いとされています。
そのため、業態に応じて自社にとって有利な計算方法を選ぶことが大切だと言えるでしょう。
免税事業者が発行する請求書への影響
インボイス制度の開始により、端数処理のルールや消費税の計算方法に変更が生じるとお伝えしましたが、この影響を受けるのは課税事業者が発行する適格請求書のみです。
つまり、免税事業者が発行する請求書においては、端数処理に関して変更はありません。
しかし、取引先が課税事業者であり仕入税額控除を受けたいと考えている場合、インボイスを発行できない免税事業者との取引を考え直すということもあるかもしれません。
現在、免税事業者として事業を行っているのであれば、インボイス制度開始に伴い免税事業者のままでいるか、課税事業者に切り替えて適格請求書発行事業者の登録を受けるかを検討する必要があると言えるでしょう。
インボイス制度開始後の請求業務を効率化するなら「invoiceAgent」
インボイス制度の開始に伴い、請求書の端数処理や計算方法が変わるだけでなく、登録番号の照合や、適格請求書とそれ以外の請求書を別々に処理しなければならなくなるなど、請求業務が今まで以上に煩雑化することが予想されています。
そして、インボイス制度開始後の請求業務の負担を軽減する手段として、請求業務の電子化が注目を集めています。
次は、請求業務の電子化を実現するソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent 電子取引(インボイスエージェント電子取引)」をご紹介します。
請求書のWeb配信で業務効率化を実現
「invoiceAgent 電子取引」は、請求書をはじめとした企業間取引文書の送受信を電子化し、業務の効率化を実現します。
PDF形式の請求書をアップロードするだけで取引先にWeb配信することができ、取引先から発行される関連帳票も「invoiceAgent」を介して受領することができます。
また、請求データのCSVファイルを所定のフォルダにアップロードするだけで、あらかじめ設定してあるルールに基づきPDFファイルを自動生成することも可能です。
また、PDFファイルをアップロードするだけで入稿・封入封緘・郵送までをお任せできる郵送サービス(オプション)もご用意しているので、Web配信と郵送を両立したハイブリッド運用にも対応できます。
インボイス制度への対応に効果的
ウイングアーク1stは、デジタル庁認定の「Peppol サービスプロバイダー」です。
「Peppol(ペポル)」とは、請求書などの電子文書をネットワーク上でやり取りするための規格で、日本のデジタルインボイスの標準仕様である「JP PINT」は「Peppol」に準拠しています。
「invoiceAgent 電子取引」は、Peppol経由のデータ送受に対応しており、請求データの「JP PINT」変換も可能です。
登録番号の確認工数削減や、業務システムとの連携による仕訳処理の自動化なども行えるので、インボイス制度への対応という面でも効果的です。
電子帳簿保存法の要件を満たすJIIMA認証製品
「invoiceAgent 電子取引」はJIIMA認証を取得しているサービスです。
請求書などの帳票を電子データとして授受・保存するには、電子帳簿保存法に対応する必要があります。
そしてJIIMA認証は、公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会が管理する認証制度で、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトウェアに与えられます。
つまり、invoiceAgentを導入することで、請求業務の電子化と電帳法対応を同時に実現することができます。
「invoiceAgent」で請求業務の効率化を実現した事例
最後に、「invoiceAgent」を活用して請求業務の効率化を実現した事例をご紹介します。
請求・支払業務をデジタルシフト(三井住友ファイナンス&リース株式会社)

国内トップクラスの総合リース会社である三井住友ファイナンス&リース株式会社は、「invoiceAgent」の導入により請求・支払業務のデジタルシフトを推進することに成功しました。
同社では従来、請求・支払業務を紙ベースで行っており、郵送によるタイムラグや印刷・発送にかかるコストが大きいという課題がありました。
また、コロナ禍に入り全社的にリモートワークを推進するなか、紙ベースの請求書発行・郵送業務が残されていることで出社しなければならない状況が発生していました。
そこで同社は、これらの課題を解消するためのシステム導入を検討開始。
電子帳簿保存法やインボイス制度への対応を視野に入れつつ、金融機関としての厳格なセキュリティ担保などを考慮した結果、「invoiceAgent」の導入に至りました。
導入後、第一弾として支払通知書の電子配信からスモールスタートし、第二弾として請求書の一部を対象に電子配信を進め、リモートワークの推進とコスト削減を実現。
引き続き帳票の電子化を推進し、最大年間1億円のコスト削減を目標に掲げています。
▼事例詳細はこちら
三井住友ファイナンス&リース株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る
請求書のWeb配信化で作業時間を3分の1に短縮(アスノシステム)

「会議室.COM」などのサイト運営事業を手掛けるアスノシステム株式会社は、「invoiceAgent」の導入により請求書のWeb配信化に成功しました。
同社では2016年、事務処理の効率化を目的にSalesforceを導入していたものの、請求書や見積書についてはエクセルやパワーポイントで担当者が手作業で作成していました。
手作業による帳票作成の負担を軽減するため、2017年にウイングアーク1stの帳票基盤ソリューション「SVF Cloud for Salesforce」を導入し、請求書や見積書をSalesforceから直接発行する仕組みを構築しました。
さらに同社は、Salesforceから発行した請求書・見積書をWeb配信するため「invoiceAgent」を導入。
請求書発行の作業時間を従来の3分の1まで短縮するなど、大きな効果を実感しています。
▼事例詳細はこちら
アスノシステム株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る
まとめ
今回は、請求書の端数処理について詳しく解説してきました。
請求書の端数処理の方法は事業者が選択できますが、記事内で紹介したようにいくつかの注意点も存在します。
また、インボイス制度の開始に伴い、請求書における端数処理のルールや消費税の計算方法に変更があり、請求業務は今まで以上に煩雑化することが予想されています。
インボイス制度開始後の請求業務を効率化したい方は、今回ご紹介した「invoiceAgent」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。