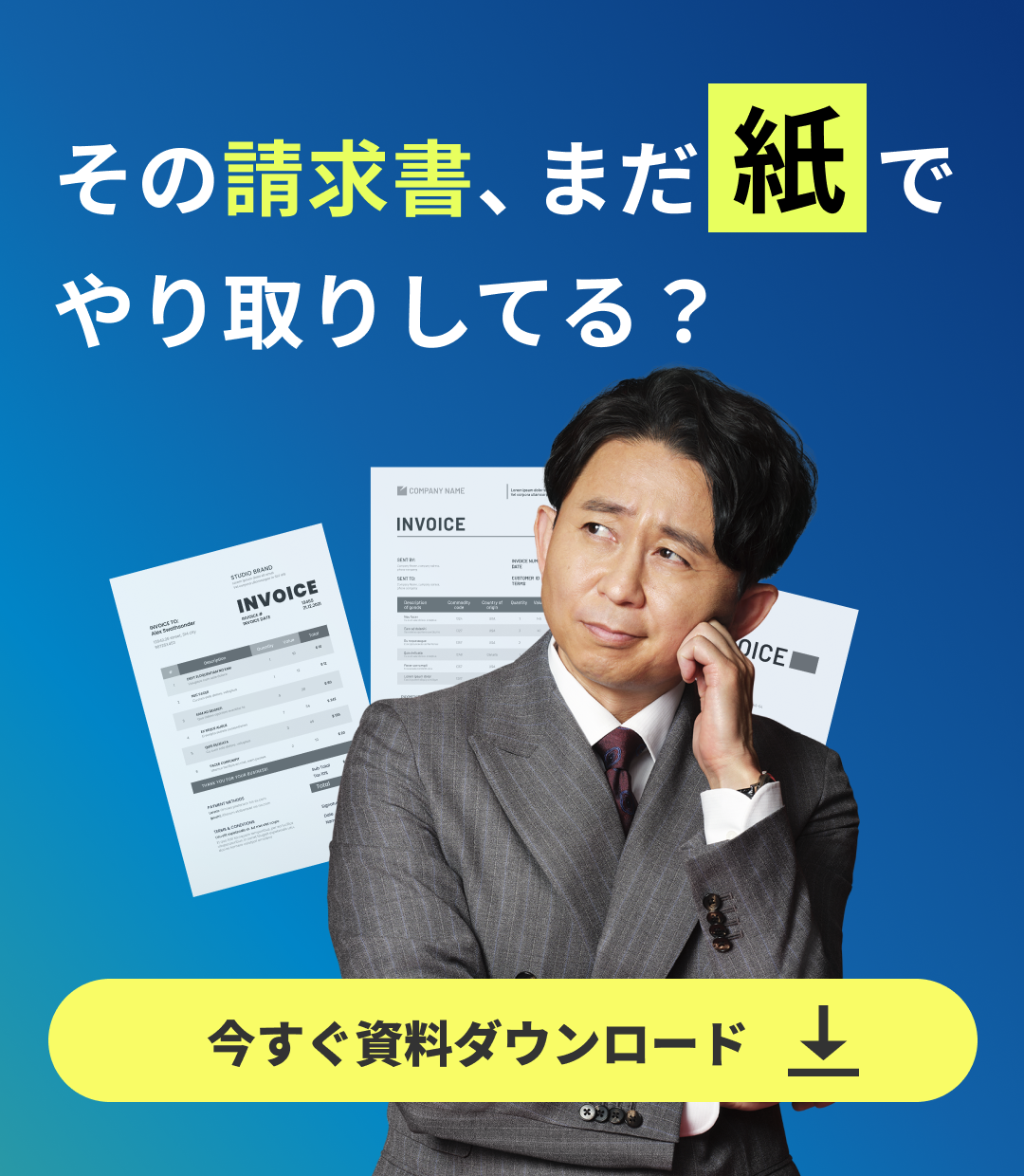請求書の受領メールは必要?
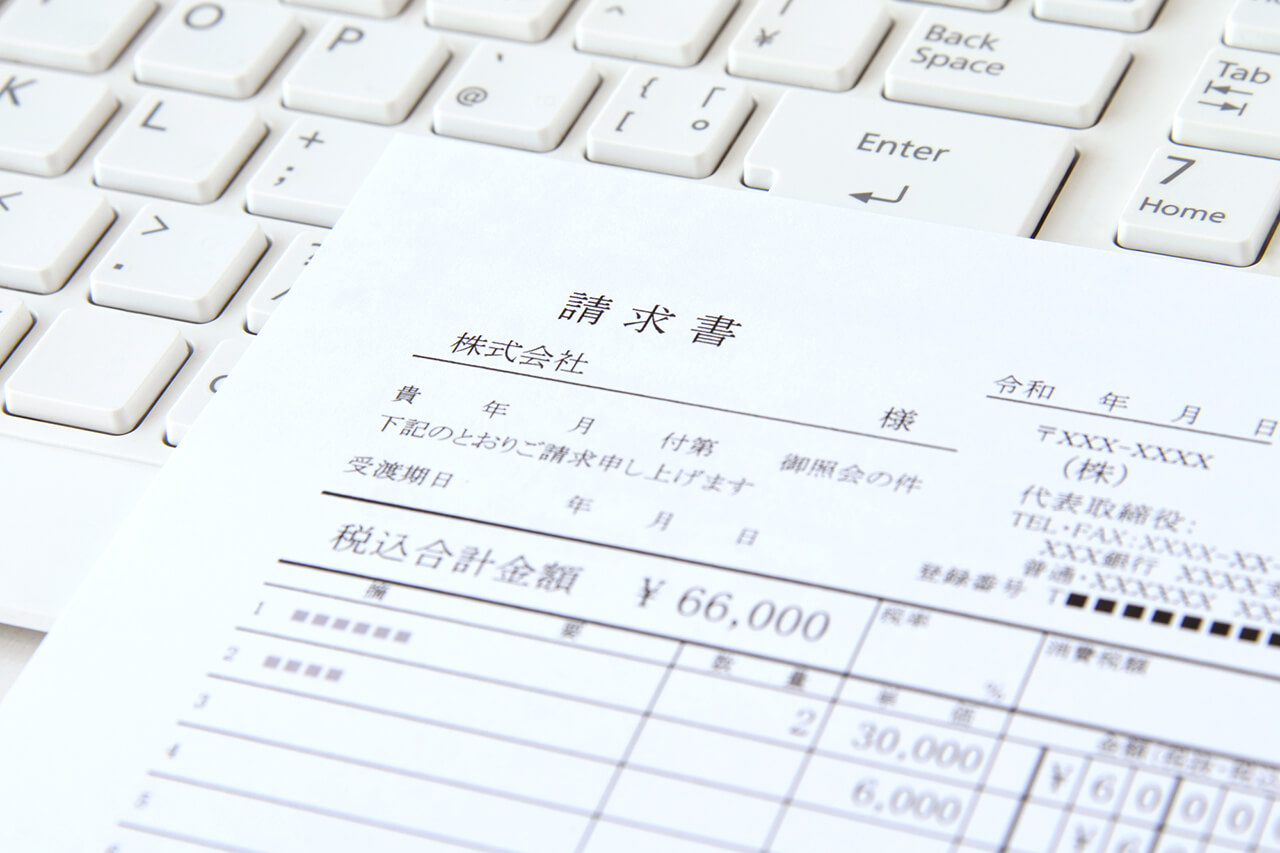
請求書の受領メールとは、取引先から送られてきた請求書を受け取った旨を、相手方に通知するためのメール。
法律上、請求書の受領メールを送る必要はありません。しかし、日本の商習慣においては、受領メールの送信はビジネスマナーのひとつとして広く認識されています。
ここでは、請求書の受領メールの必要性や役割について見ていきましょう。
トラブルの防止
請求書の受領メールを送信する主目的のひとつが、トラブルの防止です。
「請求書をたしかに受け取った」と通知することで、発行者側に安心感を与えるとともに、「送ったはず」「届いていない」といった行き違いによるトラブルを防ぐことができるでしょう。
良好な関係性の構築・維持
丁寧で迅速なコミュニケーションは、取引先との信頼関係を強化し、長期的に良好な関係性を築く上で不可欠です。請求書の受領メールを送ることも、その一環として重要な役割を果たすでしょう。
支払い処理の円滑化
メールによる請求書受領の連絡は、支払いに向けたプロセスが開始されたことを間接的に示します。請求書の受け取り後、速やかに受領メールを送ることが定着していれば、請求内容の確認や検印、支払依頼書の作成や会計システムへの入力といった後続業務へとスムーズに移行できるでしょう。
請求書受領メールの文例やマナー

次に、請求書の受領メールの文例や送信時のマナーについてご紹介します。
請求書受領メールの文例・テンプレート
請求書の受領メールの文例を確認していきましょう。
以下をテンプレートとして、実際のやり取り内容に合わせて書き方をアレンジしてみましょう。
本文:
株式会社△△
△△ △△様
いつもお世話になっております。
〇〇株式会社の〇〇です。
本日、貴社より下記の請求書を拝受いたしましたので、ご連絡申し上げます。
請求書番号:No.XXXXX
発行日:2025年5月31日
請求金額:XXX,XXX円
内容を確認の上、支払期日までに手続きを進めさせていただきます。
今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
=========================
〒123-4567
東京都〇〇区1-2-3 〇〇ビル1F
TEL:03-1234-5678
E-mail:〇〇@〇〇.co.jp
〇〇株式会社〇〇部
〇〇 〇〇
=========================
PDFなどの請求書データをメール添付にて受領した場合は、その返信として受領メールを送信します。その際は、受領した請求書データのファイル名を併記すると、より丁寧で正確な確認の意思を示すことができるでしょう。
「拝受」と「受領」のどちらを使うべき?
ビジネスでのメールのやり取りにおいては、請求書などの文書を受け取ったことを伝える表現として「拝受(はいじゅ)」や「受領(じゅりょう)」がありますが、どちらを使うべきか迷ってしまうケースもあるかもしれません。どちらも「受け取ること」を意味する言葉ですが、細かなニュアンスの違いがあります。
「拝受」とは、「受けること」をへりくだって言う謙譲語。取引先や目上の方など、敬意を示すべき相手から請求書や書類を受け取った際に用いるもっとも丁寧な表現とされています。
一方の「受領」は、 「受け取ること」を意味する一般的な表現。謙譲の意味合いは含まれないため、同等または目下の相手にも使用できます。目上の相手に対して使用しても特段失礼ではありませんが、「受領いたしました」のように丁寧な表現を用いるケースが一般的です。
どちらも請求書の受領メールに用いる表現として問題ありませんが、より丁寧な表現を選ぶのであれば、「拝受」を使用するとよいでしょう。
請求書受領メールを送る際のマナー
請求書受領メールでは、ほかのビジネスメールと同様、丁寧な言葉遣いを心掛ける必要があります。基本は「です・ます調」で統一するとともに、「迅速に送付いただき、誠にありがとうございます」や「お忙しい中、ご対応いただき感謝申し上げます」といった具体的な感謝の言葉を添えることで、誠実な印象を与えることができます。
また、請求書受領メールの送信タイミングも重要です。原則として、請求書を受け取ったら可能な限り迅速に受領メールを送信することが基本です。具体的には、請求書を受領した当日中、遅くとも翌営業日中には送信するのが理想的とされています。
請求書受領メールに対する返信は必要?
発行側(売手側)は、請求書受領メールに対して返信をするべきでしょうか?
結論から述べると、請求書受領メールに対し、さらに返信する必要は原則としてありません。受領メールは、あくまで「請求書を受け取りました」という確認の連絡であり、コミュニケーションは一区切りとなります。
ただし、メールに質問や確認事項が含まれている場合や、受領メールの内容に誤りがある場合などは返信が必要となる場合があります。
請求書受領後の業務を効率化するには?

請求書の受領後は、受領メールの送信以外にも以下のようにさまざまな作業が発生します。
- 請求書の受け取りと受領メールの送信
- 受領請求書の記載内容を確認
- 支払依頼書の作成・社内承認
- 取引内容の記帳
- 取引先への支払い・消込作業
- 請求書原本の保存
これらは金銭に関わる業務であることから正確性が不可欠であるとともに、期日までに処理を終わらせる必要があるためスピードも求められます。
そして、この一連の業務を正確かつ効率的に処理する鍵が、業務のデジタル化です。
単に請求書の受領のみを電子化するのであれば、PDF形式の請求書データをメールで受け取ったり、請求書受領システムや請求書受領サービスを利用することで実現可能です。しかし、請求書の受領のみを電子化しても、業務の正確性や効率性の面で効果は限定的であり、担当者の負担を大きく軽減することはできません。
そのため、受領請求書に関わる業務を抜本的に改善するには、後続業務も含む一連の業務プロセスをデジタル化する仕組みを構築することが重要です。
「invoiceAgent」で請求書に関わる業務を効率化
次は、請求書の受領や後続業務を効率化するソリューションとして、ウイングアークが提供する「invoiceAgent(インボイスエージェント)」をご紹介します。
請求書データの配信・受領なら「invoiceAgent 電子取引」
「invoiceAgent 電子取引(インボイスエージェント 電子取引)」は、請求書などの帳票データの配信・受領を実現するソリューションです。
PDF形式で帳票をアップロードするだけで取引先に配信することができ、取引先が発行する請求書などの帳票も「invoiceAgent」を介して受領できます。アップロードした帳票データが無事にダウンロードされたかどうかを確認できるので、受領メールでの通知に代えることも可能です。
また、デジタルインボイスの規格である「Peppol」経由のデータ送受信に対応しており、受領した適格請求書のデータ化や適格請求書発行事業者の登録確認も可能なので、インボイス制度への対応という面でも有効です。
紙で受領した請求書のデータ化なら「invoiceAgent AI OCR」
「invoiceAgent AI OCR(インボイスエージェント エーアイ オーシーアール)」は、紙で受領した請求書などのデータ化を実現するソリューションです。
高精度な複数のOCR/AI OCRエンジンを搭載しており、読み取り文書の様式や特徴に応じて適切なOCR/AI OCRエンジンを選択したり、複数のOCR/AI OCRエンジンによる処理を実行し、結果を比較したりすることも可能です。
また、読み取り文書の歪みや傾きを自動補正する機能も備えているので、認識率の低下を防ぎつつ効率的にデータ化を推進することができます。
法令に準拠した一元管理なら「invoiceAgent 文書管理」
「invoiceAgent 文書管理(インボイスエージェント 文書管理)」は、法令に準拠した文書データの一元管理を実現するソリューションです。
「invoiceAgent」などのウイングアーク製品で出力・データ化した帳票はもちろん、他システムで出力した帳票データもまとめて取り込み、事前に設定したルールに従い自動で仕分け・保存を実行します。保存したデータは、さまざまな条件で検索することができ、電子帳簿保存法で求められる検索要件にも対応可能です。
また、文書の保存期間に応じた自動削除機能や、強固なガバナンス構築に有効な証跡管理機能を備えているのも特徴です。
「invoiceAgent」で請求書受領を効率化した事例
最後に、「invoiceAgent」を導入して受領請求書に関わる業務を効率化した事例をご紹介します。
請求書の電子受領を実現し「デジタル経営」を推進(西武ホールディングス)

株式会社西武ホールディングスは、「invoiceAgent」を導入して請求書の電子受領を実現しました。
グループ全体で「デジタル経営」を推進している同社は、ERPパッケージ「Biz∫」を導入するなど以前から会計システムの刷新に取り組んできました。しかし当時は電子帳簿保存法への対応ハードルが高く、取引先から受領する請求書のペーパーレス化に関しては先送りとなっていました。
ところが、コロナ禍に突入したことでテレワークの必要性が高まり、請求書のペーパーレス化についても"待ったなし"の状況に。検討の結果、「Biz∫」との連携が容易で、企業間取引文書の電子化および送受信、さらに電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応できる点を評価し、「invoiceAgent」の導入を決めました。
「invoiceAgent」の導入後、取引先がPDF形式で発行した請求書をアップロードするだけで、スムーズに受領できる仕組みが完成。現在はグループ内23社に「invoiceAgent」を展開し、最終的には40社への展開を想定するなど、グループ全体のデジタル経営推進に大いに役立てられています。
▼事例詳細はこちら
株式会社西武ホールディングスのinvoiceAgent導入事例をもっと見る
電帳法に準拠した請求書受領の業務フローを構築(住友不動産)

住友不動産株式会社は「invoiceAgent」の導入により、電子帳簿保存法に準拠した請求書受領の業務フローを確立しました。
紙文化が根強い不動産業界において、社内の申請書類など一部のビジネスプロセスで電子化に着手するなど、かねてよりペーパーレス化の推進に取り組んできた同社。そうしたなか、電子帳簿保存法の改正がきっかけとなり、取引先から受領する請求書を改正電帳法の要件に対応する形で電子保存する仕組みを構築することに。システム選定の結果、JIIMA認証製品であることや、AI OCR機能を利用できる点、導入実績の豊富さなどを評価し、「invoiceAgent」の導入に至りました。
導入後、受領請求書を電帳法に準拠する形で電子保存する仕組みが完成。現在、グループ全体で約700ユーザーが利用しており、年間約3万枚規模の請求書の電子保存を見込んでいます。また、支払い承認プロセスを電子化したことで押印の手間や承認待ちの時間が削減され、業務スピードの向上にも効果を得ています。
▼事例詳細はこちら
住友不動産株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る
まとめ
今回は、請求書受領メールに焦点を当て、書き方や送り方のマナー、文例などをご紹介しました。
請求書受領メールは、取引におけるリスク管理や良好な関係性の構築といった観点で有用です。一方で、請求書の受領後は多くの後続業務があることから、担当者の負担は小さくありません。そこでおすすめしたいのが、請求書受領のデジタル化です。
請求書関連の業務に課題を感じている方は、記事内でご紹介した「invoiceAgent」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。