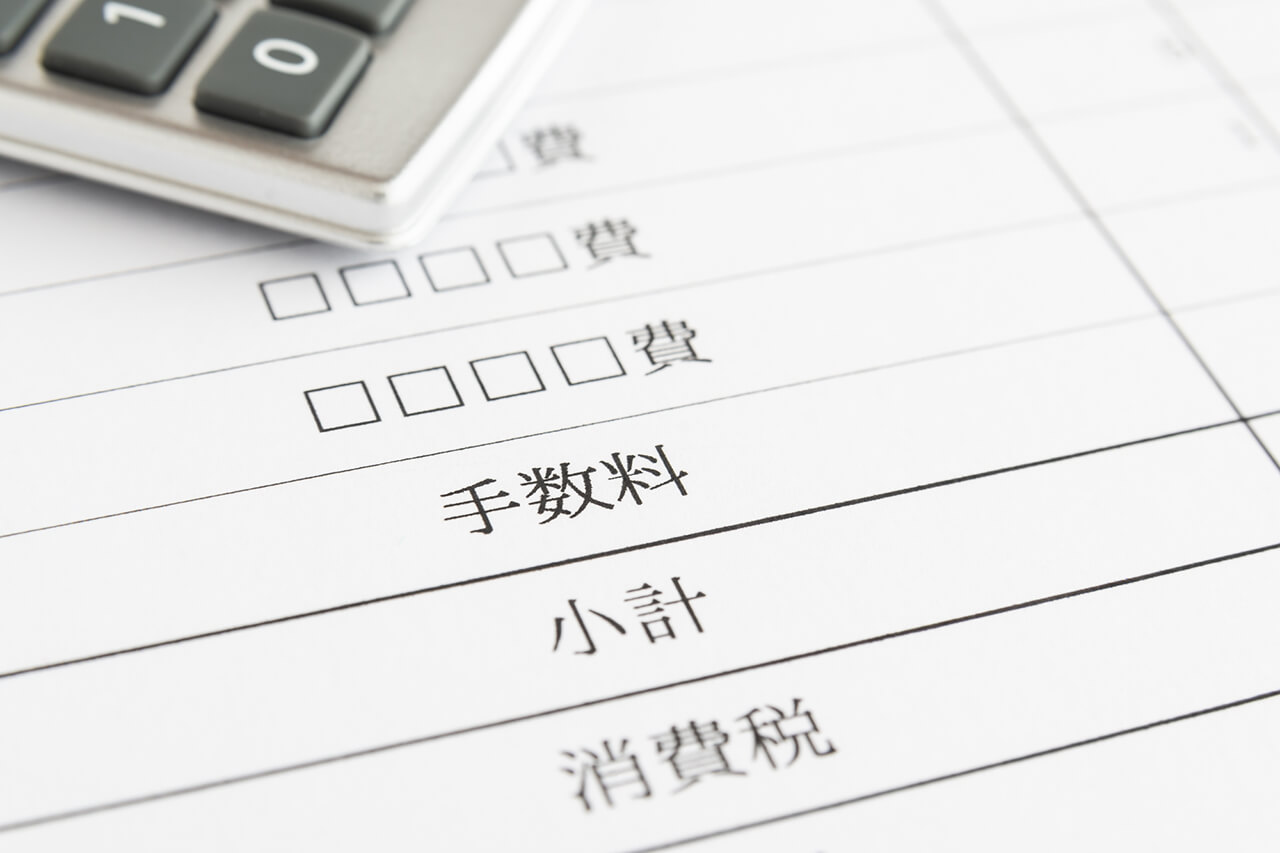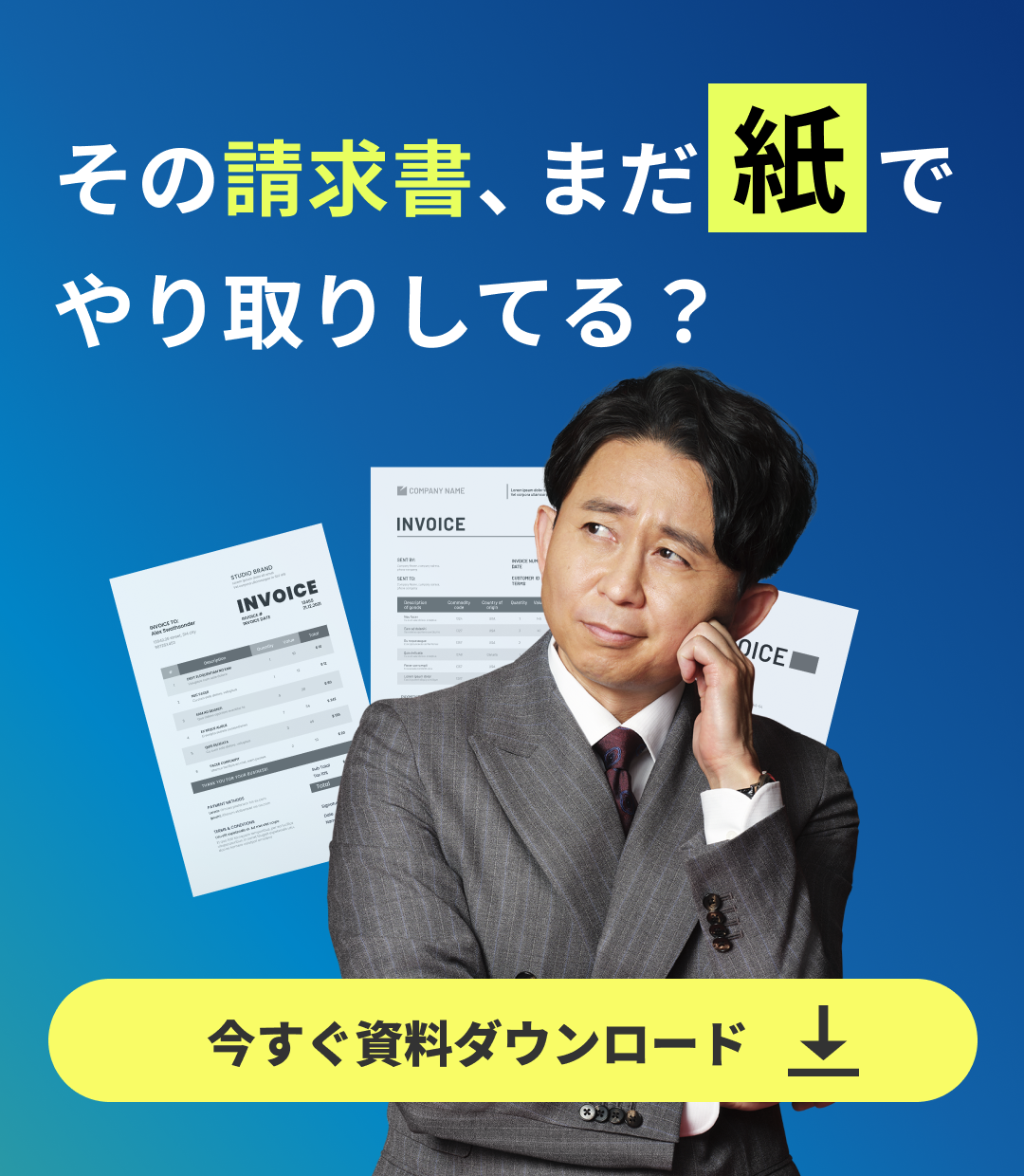請求書には消費税の記載が必要
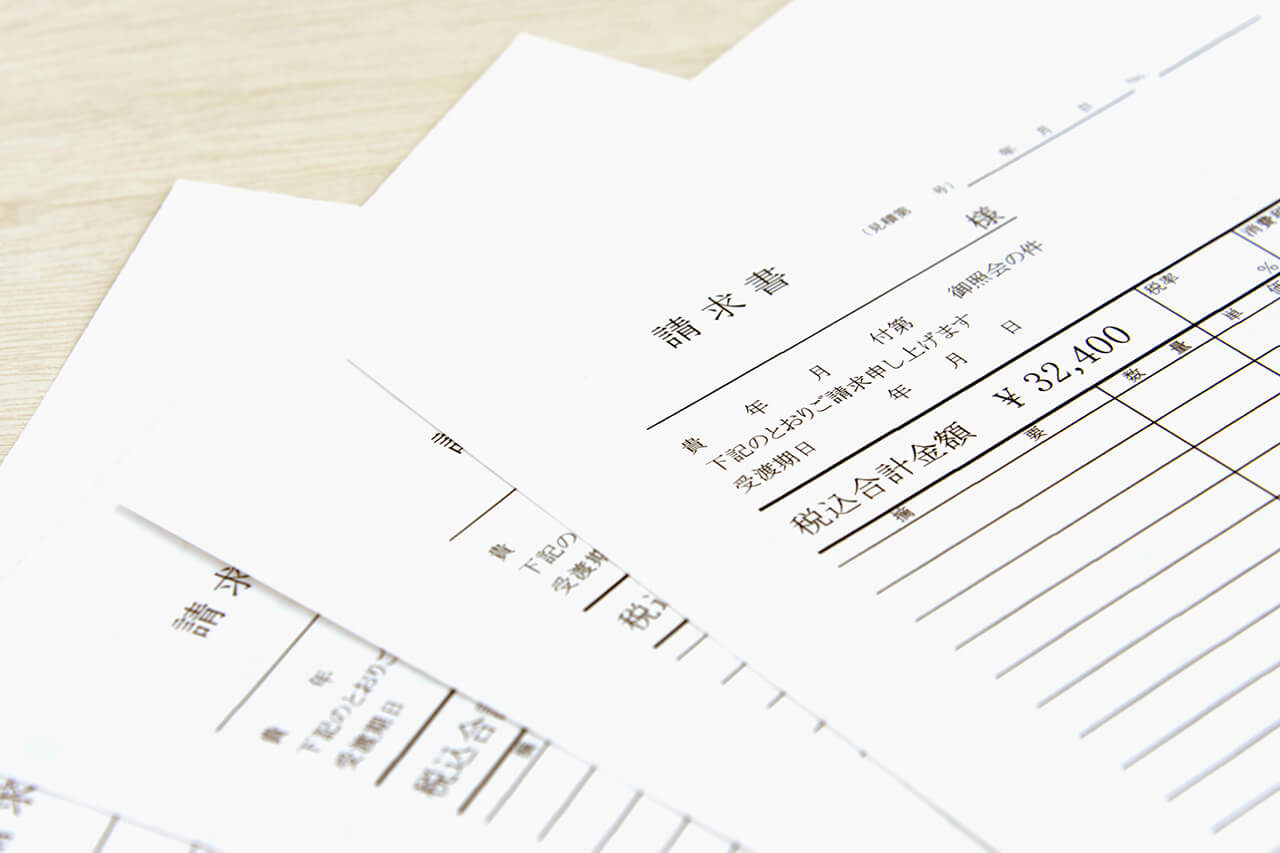
結論から述べると、請求書には消費税の記載が必要です。
消費税は間接税であり、本来の納税者である消費者ではなく、消費者から消費税を預かった事業者が納税を行います。
その際、事業者は「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入等に係る消費税額」を差し引いて納税額を算出します。
これは、消費税の二重課税を防ぐための「仕入税額控除」という仕組みです。
つまり事業者は、「売上取引で預かる消費税額」と「仕入取引で支払う消費税額」を正確に把握する必要があります。
そして、これらの消費税額を把握し、納税額を適切に算出するための証拠書類となるのが請求書です。
消費税法では、課税事業者が仕入税額控除を受けるには、課税仕入れなどに関する帳簿および請求書等を保存しなければならないと定められています。
請求書の消費税額に関するよくある疑問

次は、請求書の消費税額に関するよくある疑問として、以下を確認していきましょう。
- 請求書への消費税の書き方は内税・外税?
- 請求書に記載する消費税の端数処理の方法は?
- 消費税が記載されていない請求書を受け取った場合は?
請求書への消費税の書き方は内税・外税?
商品やサービスの価格表示の方法には内税(税込み表示)や外税(税別表示)がありますが、請求書に消費税を記載する際、内税にするべきか、あるいは外税にするべきか迷ってしまう場合もあるでしょう。
不特定かつ多数の者に対する値札や店内掲示などにおいては消費税を含む総額表示が義務付けられていますが、請求書においては総額表示義務の対象ではありません。
つまり、内税で記載するか外税で表示するかは、発行者が任意で決めることができます。
ただし、請求金額をわかりやすく示すためにも、最終的な請求金額は税込みの合計金額を記載するようにしましょう。
請求書に記載する消費税の端数処理の方法は?
販売する商品・サービスの金額や適用税率によっては、消費税額に1円未満の端数が生じることがあります。
消費税に端数が生じた場合、以下のいずれかの方法で端数を処理して請求書に記載するのが一般的です。
- 切り上げ
- 切り捨て
- 四捨五入
どの方法で端数処理を行うかは事業者の判断に委ねられていますが、社内で端数処理の方法を統一しましょう。
また、従来の「区分記載請求書等保存方式」においては、消費税の端数処理の回数について明確なルールは存在しません。
そのため、品目ごとに端数処理を行っても、税率ごとに端数処理を行っても問題ありません。
ただし、詳しくは後述しますがインボイス制度では端数処理の回数についてルールが設けられているため注意が必要です。
消費税が記載されていない請求書を受け取った場合は?
取引先から受領した請求書に、税率や消費税額などが記載されていない場合、以下のような対応が求められます。
- 必要事項が記載された請求書の再交付を依頼
- 取引の事実に基づき必要事項を追記する
時間がたってから再交付を依頼したり必要事項を追記するのは確認に時間が掛かるため、請求書を受領したら速やかに記載内容を確認するようにしましょう。
インボイス制度による請求業務への影響

ここまで、請求書には消費税の記載が必要とお伝えしてきましたが、2023年10月のインボイス制度(正式名称:適格請求書等保存方式)の開始後は消費税の記載事項が変更になりました。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除に関する制度のこと。
以下の記事では、インボイス制度の概要や開始後の変更点を詳しく解説しているので、あわせてお読みください。
消費税に関する記載事項が追加
インボイス制度の開始後、課税事業者が仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)の保存が必要になり、請求書への記載事項も以下のように変更されます。
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額、および適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)適格請求書発行事業者の氏名または名称、および登録番号
(※太字部分が「インボイス制度」開始後の追加箇所)
消費税に関わる変更としては、税率ごとに区分して合計した対価の適用税率、税率ごとに区分した消費税額等を記載しなければならなくなりました。
適格請求書の記載事項については以下の記事で詳しく解説しているので、合わせてお読みください。
端数処理の回数は「税率ごとに1回ずつ」に
従来の区分記載請求書等保存方式では、消費税の端数処理の回数については発行者に委ねられているとお伝えしました。
インボイス制度の開始後、「ひとつの適格請求書のなかで、税率ごとに1回ずつ端数処理を行う」というルールが加わります。
なお、切り上げ・切り捨て・四捨五入といった端数処理の方法については、これまで同様事業者の判断に委ねられています。
インボイス制度への対応なら「invoiceAgent 電子取引」
インボイス制度の開始後、請求書への消費税の記載方法や端数処理のルールに変更が生じるとお伝えしました。
さらに、適格請求書とそれ以外の請求書で仕分けを行ったり、適格請求書の要件を満たしているか確認したりする作業が発生するため、今まで以上に請求書関連業務が煩雑化すると予想されています。
そうしたなか、インボイス制度開始後の負担軽減を図り、請求書関連業務の電子化に着手する企業が増えつつあります。
次は、請求書関連業務の電子化を実現するソリューションとして、ウイングアーク1stが提供する「invoiceAgent 電子取引(インボイスエージェント 電子取引)」をご紹介します。
アップロードするだけで請求書の送受信が可能
「invoiceAgent 電子取引」は、請求書などの企業間取引文書の送受信を電子化するソリューションです。
PDFファイルをアップロードするだけで文書データをWeb配信することができ、取引先が発行する帳票も「invoiceAgent」を介して受け取ることが可能です。
また、請求情報がまとまったCSVファイルを所定のフォルダにアップロードすれば、指定した様式で請求書のPDFファイルを自動生成することができます。
取引先ごとに私書箱が設置され、複数の取引先とのやり取りを「invoiceAgent 電子取引」に集約することができるので、企業間取引の効率化・迅速化につながります。
また、オプションの郵送サービスも提供しているので、Web配信と郵送のハイブリッド運用も可能です。
インボイス制度・電子帳簿保存法への対応を支援
「invoiceAgent」は、電子帳簿保存法の要件を満たすソフトウェアの証である「JIIMA認証」を取得しています。
そのため、送る側・受け取る側どちらの電子帳簿保存法対応も支援します。
また、インボイス制度への対応という面でも有効です。
「invoiceAgent」は、デジタルインボイスの標準規格である「Peppol」経由のデータ送受信に対応しているほか、受領した適格請求書のデータ化や適格請求書発行事業者の登録確認も「invoiceAgent」で行えます。
インボイス制度を見据えて「invoiceAgent」を導入した事例
最後に、インボイス制度への対応を見据えて「invoiceAgent」を導入した企業事例をご紹介します。
請求・支払業務をデジタルシフト(三井住友ファイナンス&リース株式会社)

国内トップクラスの総合リース会社である三井住友ファイナンス&リース株式会社は、「invoiceAgent」により紙ベースで運用していた請求・支払業務をデジタルシフトすることに成功しました。
同社では従来、リース契約の請求・支払業務を紙ベースで行っており、郵送によるタイムラグや印刷・発送にかかるコストが課題視されていました。
さらに、コロナ禍に突入したことで全社的なリモートワークが進むなか、紙ベースの請求書発行・郵送業務が出社しなければならない要因となっていました。
そこで同社は、請求・支払業務をデジタルシフトするためのシステム導入の検討を始めました。
システム選定においては、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応を視野に入れつつ、厳格なセキュリティなどを考慮した結果、「invoiceAgent」を導入することになりました。
導入後、支払通知書の電子配信からスモールスタートし、続いて請求書の一部を対象に電子配信を開始し、請求・支払業務のデジタルシフトを推進。
今後はさらに電子配信の適用範囲を広げていき、最大年間1億円のコスト削減を目指しています。
▼事例詳細はこちら
三井住友ファイナンス&リース株式会社のinvoiceAgent導入事例をもっと見る
グループ全体の「デジタル経営」を見据えた経理業務の改革(西武ホールディングス)

グループ一丸となってデジタル経営の推進に取り組む株式会社西武ホールディングスは、受領する請求書の電子化を図り「invoiceAgent」を導入しました。
同社ではかねてより会計システムの刷新を進めており、2019年にNTTデータ・ビズインテグラルのERPパッケージ「Biz∫」を導入していました。
しかし、2019年当時は電子帳簿保存法の対応ハードルが高く、取引先から受領する請求書のデータ保存については先送りとなっていました。
そうしたなか、2020年の新型コロナウイルス感染症の流行拡大、そして2022年1月に電子帳簿保存法が改正されることが決定したこともあり、受領する請求書のペーパーレス化に舵を切ることとなりました。
システム選定においては、すでに導入しているERPパッケージ「Biz∫」との連携が可能で、なおかつインボイス制度や電子帳簿保存法に対応可能な点がポイントとなり、「invoiceAgent」の導入を決定。
これにより、取引先がPDF形式で請求書を発行・アップロードするだけで、請求書データを受領・保存できる仕組みを実現しました。
現在、グループ23社で「invoiceAgent」の利用が進められており、最終的にはグループ40社での導入を予定するなど、グループ全体のデジタル経営推進に役立てられています。
▼事例詳細はこちら
株式会社西武ホールディングスのinvoiceAgent導入事例をもっと見る
まとめ
今回は、請求書の記載項目のひとつである消費税に焦点を当て、記載する必要性や計算方法、インボイス制度による影響などを解説しました。
請求書は、消費税の納税額を算出するために必要な証拠書類であり、請求書への消費税額の記載は法律でも定められています。
また、インボイス制度の開始後は消費税に関する記載事項が追加され、事務処理も今まで以上に煩雑化することが予想されています。
インボイス制度開始後の業務負担を軽減するためにも、記事内でご紹介した「invoiceAgent」で請求書関連業務の電子化・効率化に取り組んでみてはいかがでしょうか。